 >既刊の紹介>岡山県畜産史
>既刊の紹介>岡山県畜産史 >既刊の紹介>岡山県畜産史 >既刊の紹介>岡山県畜産史 |
1.牛市場の発達
家畜市場は,すでに平安朝末期に上代の牧制がくずれ,牧の荘園化によって私牧が成立し,貢献の余剰が地方の定期市場に売り出されたときから,かなりの発達をみた。
産牛地である中国,近畿の家畜市場は,交易のための自然発生的なものを,領主が許可育成したものが多かったが,近世(1560-1860)にはいると,これを領主が統制するものが多くなった。摂津天王寺市は,市場の統制管理を民間の有力者にまかせ,天正12年(1584)牛馬売買御免の証を受けて石橋孫右衛門が特権的に代々その任に当たった。備中松山市場は,寛永のころ,(1624-43)領主自身が市場を開設し,町年寄に市場を管理させた。千屋市場は,鉄山師太田辰五郎によって天保5年(1834)開設され,市場の経営も太田辰五郎が行なった。伯耆大山市は,祭礼の場に商人と牛馬が集って,近世初期,享保5年(1720)開市された。このように牛馬市場の開設とその運営については諸種の形態があった。
牛の交易は,鎌倉期以降中世に至って,領主武士階級の軍馬の調達のための馬市による刺激と,農耕運搬に,牛の使役が一層発達することによって牛馬市が発達し,中世末期には京都,奈良をはじめ摂津天王寺牛市,安芸吉田市,伹馬養父市などが,名主層の農用牛馬あるいは鉄山その他の運搬用の需要の拡大によって,牛馬の卸売りを行う集散地市場として発達した。
摂津天王寺牛市は,単に市場としての性格だけでなく,中央消費地への大供給市場として,近畿はもちろん,中国,四国さらには九州からの商人が集まった。近世になると地方の産牛地の要所においても,このような大市場が形成された。古くは天暦5年(951)に開市された備後久井の市および近世初期享保5年(1720)開市された伯耆大山市(これらはのちに石見出羽市とともに中国地方三大牛市といわれた)がそれであった。
このような産牛地に接する大集荷市場は,近世になって農民層における農耕と運搬の需要が一層大きくなり,また,牛の飼養が繁殖,育成,使役と地帯分化するに従って,生産地から消費地への中継の必要から発生したのであるが,後に産地小市場の開設に伴い,独自の機能をもつものに発展し,消費地市場,産地市場および中継地市場というように機能分化が進められた。
近世までの和牛の流通と市場,市場の管理と経営方法,牛の価格等については,斉度英策(1965)の『近世和牛経済史』,石田寛(1961)の「岡山藩における牛馬市ならびに牛馬に関する考察」(瀬戸内研究,第13,14号合併号),石田寛ら(1960)の「大山博労座(牛馬市研究第2報)」,石田寛ら(昭和33年)の「中国地方山間盆地牛市の研究(岡山県久世牛市の場合)」などに詳述されている。
2.藩政時代までの牛馬市場
岡山県内務部(昭和3年)の『岡山県畜産要覧』によれば,牛馬市場は今から約1,200年前,文武天皇の慶雲2年(705)に美作において開市(注 一宮市場)されたようだとある。これによれば,前述の平安末期(1180年代)より約500年もさかのぼることになる。なお,この文献および石田寛(昭和36年)の『明治以後「登り牛」の流通構造-大登り,相登りを中心にして-』により,これらに掲げられている往年の市場名と開設年などについて述べれば次のとおりである。
まづ,岡山藩においては,年間100頭以下の取引頭数という小市場がほとんどで,11市場が挙げられている。
一宮馬市(御津郡一宮村 現岡山市)元禄2年(1689),岡山藩の創設になり,専ら藩の乗馬を交換したものである。廃藩後一時廃絶したが,明治11年(1878)2,3の有志により再興した。しかし,現在(注 昭和3年)はまた廃絶している。
西片上村牛馬市(和気郡片上町 現備前市)その開設がいつかはっきりしないが,宝永4年(1707)には片上八藩宮祭礼に際して,8年9日から17日まで開市した。そして,いつのまにか中絶したが,享保20年(1735)から毎月6日および8日,祭礼には前後10日開市することにした。ところがまた中絶し,享和2年(1802)再び開場した。
加茂市場村牛馬市(御津郡加茂村 現加茂川町)延享3年(1746)開設された。
藤野村牛市(和気郡藤野村,現和気町)安永元年(1772)開設し,文化12年(1815)再興している。
辛川市場村牛馬市(御津郡一宮村 現岡山市)文久3年(1863)の創設であるが,元治年間(1864)までは一宮村馬市に続いて隆盛であった。
上田村西分牛交易(津高郡上田村,現加茂川町)弘化2年(1845)上田村西分鎮守魔法宮(牛馬守護神)に近郷から牛を引きつれて参詣することが初まりとなって開設された。
建部新町牛馬市(御津郡建部村 現建部町)元禄10年(1697)の開設であるが,その後宝永6年(1709)および天明3年(1783)に再興した。
周匝村牛馬市(赤磐郡周匝村 現吉井町),享保19年(1734)の創設であった。
金川牛馬市(御津郡金川村,現御津町)その起源はつまびらかにできないが,宝永5年(1709)の火災により中絶したものを,宝暦10年(1760)再開した。
矢田村牛市(和気郡山田村 現吉井町)安永2年(1773)開設した。
福岡村牛馬市場(現邑久郡邑久町)天保7年(1836)開設した。
なお,岡山藩以外には次のような市場があげられている。
松山市場(上房郡松山村 現高梁市)元禄2年(1689)に開設された。この市場については別に詳述することにする。
井村市場(阿哲郡上市村 現新見市)明和年中(1764-71),播州龍野藩の支配のころ創設された。
小坂部市場(阿哲郡刑部村 現大佐町)起源ははっきりしないが,古老の口碑によれば元録年間(1688-1703)にはじまったということである。斉藤英策(1965)の『近世和牛経済史』によれば,天保(1830-43)のころ小坂部村清水の牛馬商藤井甚三郎によって開設され,作州から千屋へ行く博労相手に大佐山の北麓の大山神社前で菅生市の前日開市したが,余りにも不便なところであったので,数年後に閉市したということである。
菅生牛馬市(菅生村 現新見市)西谷の西谷幾三郎の世話によって,居宅の前の道路で開市した。開設年次をつまびらかにできないが,千屋市の創設後に続いて開かれたものと伝えられている。千屋市場の前市として,千屋市の日の前日と前々日の2日間,春秋2回開市した。
油野市馬 江戸中期,油野村(現神郷町)下油野の酒造業福田国治の開設による。油野は伯耆から南下する要所に当たるので,一時は盛況を呈し,明治時代まで続いた。開市がいつかはっきりしないが,安政6年(1859)6月にはすでに開設されていた。
高瀬野原牛馬市 高瀬村(現神郷町)野原は,小早川隆景が戦争用の役駄を飼育したところといわれている。備中と伯耆との交流点に当たり,両国からここへ牛馬を持ち寄って開市した。この市場は釜村(現神郷町)の蔓牛博労が開設したもので,安政6年(1859)にはすでに開設されていた。
美甘市場(真庭郡美甘村) 口碑によれば慶長9年(1604)藩主森忠政の時代から運上金を上納したという。当時は近傍5ヵ所を除くほか開設を許可しなかったということで,寛政年間(1789-1800)が最も盛大であって,1ヵ年牛馬売量3万頭以上に及んだ。小坂部市場と同年代の開設である。
一宮市場(苫田郡一宮村 現津山市) 今から約1,280年前の慶雲2年(705),中山神社鎮座のとき,四方から馬をひいて来て売買したのにはじまるわが国でもっとも古い市場で,久世市場と同じく東牛の大中継市場となった。現在(注 昭和3年)の常設宮之市家畜市場がこれである。この市場については別に述べる。
また,勝山町史編集委員会(昭和49年)の『勝山町史』(前編)によれば,「農牛と牛市」と題して,「古来農牛は耕作の原動力で,農家にとって田地につぐ財産であった。使牛1頭持つか持たないかは,一人前の百姓であるかないかをきめるほどのものであって,売買,貸借,質入れなど生計上重大な関係をもっていた。牛の購入は常時馬喰によるものと,牛市によるものとがあり,有名な大山市のほか,勝山領内には土居市(湯原町禾津)と鹿田市(落合町)があった。土居市は毎年4月27-29日と8月16-18日の2回,鹿田市は毎年4月19-22日と7月28日から8月1日までの2回開かれ,両市には藩の役人が出張して治安に当たり,近傍の人は草を刈って市場に売り,小銭を稼ぐのが例となっていた。」ということである。
ここで岡山県における牛馬の流通上重要な役割りをもった大市場についてやや詳細に述べれば次のようである。これらの中には,高梁市場のように,現在全国的に有数な大市場として機能しているものもある反面,大山市場や千屋市場のように往年の繁栄は今は語り草に過ぎないものもある。
高梁家畜市場
この家畜市場は,寛永(1624-43)の末ごろ,備中松山城主水谷伊勢守勝隆の創設した松山牛馬市にはじまる。
水谷氏は寛永16年(1639)から元禄7年(1694)まで56年間続いた。初代勝隆,2代勝宗,3代勝美と継承されたが,勝美に嗣子がなく,徳川幕府のきびしいおきてによって城地は没収された。勝美の弟勝時に新地3,000石を賜って,やっと命脈を保った。このとき有名な大石内蔵之助の松山城受取りの事件があった。
水谷氏は歴代松山城主の中で最も殖産興業に力を尽くし,多くの事績を後世に残した。まず,入城第一に中国山脈に近い地域の砂鉄の採集に着目し,一方,新田の取立てに意を用いた。牛馬の増産奨励方法として,また,城下の繁栄と藩の収入の増加を目的として牛馬市を開設した。
はじめは槿垣の南側の土地に抗を打って牛馬のけい場とし,売買は南町の街路上で行なった。開市中は一般民家の通行を禁止した。管理者として中曽屋一族を指名し,市場の管理権を委任した。管理者は問屋口銭と称して手数料を徴収し,藩としては管理者から上納を申しつけていたようである。
水谷氏の断絶のあと,安藤,石川両藩士を経て(この間およそ50年),板倉氏が藩主となったとき,石川氏からの引継書に,牛馬市場管理者の徴収していた問屋口銭は,牛馬1頭につき8分4厘であったという記録はあるが,藩主が利益金を上納させた記録は見当たらない。しかし,なんらかの名目で課税したことは想像される。ただ,水谷氏の菩提寺の畳がえを,中曽屋に申しつけた記録はある。その後,中曽屋は為長屋と名のるようになり,分かれて5軒となったが,引続き市場の管理権を認められていた。
明治維新になって,藩の廃止により,市場の管理権は完全に為長屋一族の掌握するところとなった。明治7年(1874),街路上で開市することが禁ぜられたので,為長屋一族の宅地内あるいは耕地内で取引きが行なわれた。明治18年(1885)には衛生上の取締りから,人家,井戸をへだたる20間以内での取引きを禁止されたので,これを契機として現在地に家畜市場を新設した。明治43年(1910)3月,家畜市場法(法律第1号)が公布されたのに伴い,管理者も為長屋一族が「合資会社高梁定期家畜市場」を組織して経営に当たり,内容も漸次整備した。
大正14年(1925),時代の趨勢にかんがみ,その筋からの勧奨により,前記私法人管理者から公益法人である上房郡畜産組合に移管された。昭和17年(1942)12月,岡山県農業会の経営するところとなり,戦後,昭和23年(1948),農業会解散により,改めて上房郡畜産農業協同組合連合会の管理するところとなった。現在は岡山県経済連の管理となっている。
この家畜市場は,寛永20年(1643)に創設されたとみても,現在までに約350年を経過したことになる。(以上『高梁家畜市場の沿革』による)
この市場には古くから備中北部の牛の主産地である阿賀,哲多,川上の各郡から牛が集められた。元禄年代(1688-1703)に領主により開設された新見市場に阿賀,哲多両郡産牛が集められ,その後市である千屋市場で取引きされたものがこの松山市場に入場し,西牛に向くもののほか,東牛として近畿方面へ転売するものもかなりあった。また,中国の産牛地から四国へ送られる牛は,この市場を拠点として,玉島港経由で送られるものが多かった。
この市場における取引成績は後述するとおりであって,昭和年代になるとつねに1万頭をこえる盛況を呈し,とくに最近1,2年は3万頭をこえ,全国有数の規模を誇るようになった。これは,昭和46年(1971)7月から,全面的にせり取引きとするなど,つねに市場運営の近代化に務めたことが,取引関係者に評価されたことによるものと思われる。
千屋牛馬市
 千屋牛馬市は,阿賀郡実村(現新見市千屋)の太田辰五郎が天保5年(1934)に開設したもので,辰五郎が経営者であった。天保(1830-43)のころ開かれた阿哲郡内の産地小市場,すなわち菅生市場,小坂部大佐市場,油野市場,高瀬野原市場などは,いずれも千屋牛の前市として開かれたものであった。
千屋牛馬市は,阿賀郡実村(現新見市千屋)の太田辰五郎が天保5年(1934)に開設したもので,辰五郎が経営者であった。天保(1830-43)のころ開かれた阿哲郡内の産地小市場,すなわち菅生市場,小坂部大佐市場,油野市場,高瀬野原市場などは,いずれも千屋牛の前市として開かれたものであった。
千屋市場の経営は,必ずしも順調とは行かず,経営難におちいったこともあったようであるが,辰五郎の財力と熱意と知恵とをもって経営が続けられた。その経営方法は次のようなものであった。
① 地方の産牛を市場へ多数集めること。
自家および親類の持牛すべてを市場に集め,牛の品評会を開き,優秀なものに賞品を与え,また,持牛をはじめ出場牛の中から選び出した牛に闘牛を行わせて人集めとした。
② 伯耆,出雲,備後各地の牛持や商人に宣伝して多数の客を集めること。
付近の農家へ客を宿泊させ,食糧その他必需品を市価より安く提供した。また,遠くからの入場牛を付近の農家に収容させ,飼料代などを補助して安くさせ,長逗留できるようにした。
③ 地方の博労を引き立てること
弘化年中(1844-47)に市況が不振になったので,地方の博労に資金を低利で年賦制で貸与し,平素からその活動をうながし,市場開設日には地方の牛を多数出させるようにした。
市場の開市日は,古老の口碑によれば,半夏市が7月はじめ5日間位,秋の大市が11月20日から1週間ないし10日ぐらいであったという。昭和35,6年(1960-61)ごろ,著名な作家井伏鱒二が『取材旅行』という著作の中に「千屋の牛市」を書いている。この取材に現地を訪れ,古老から昔の牛市の話をきいたとき,筆者も同道したが,そのときの話では,秋の大市の最盛期には,1,000頭を超える取引きが行なわれたということで,そのころは付近の田圃一面に杭を打って牛をつなぎ,1週間も10日も取引きが行なわれたということであった。この状態は昭和初年まで続いたということである。開市の期間中は,露店が立ち並び,近郷からの人出でにぎわい,農家は牛を売った金で冬物の衣類や家財道具,農具などを買った。牛を追って一家総出で出かけるのは,牛代金を主人に飲食などに浪費されないよう監視するためでもあった。大牛持ちは開市の期間中逗留して,小作人の牛の売買の世話をし,飲食をふるまったということであった。昭和36,7年(1961-62)ごろになると大市に集まる牛はわずかであったが生活物資の市場の方はまだ何日間か開かれていた。
明治16年(1883),千屋牛馬会社が設立され,これによって市場の経営が行われた。
鉄山業の衰微した明治中期ごろから,中国山地では和牛の生産が一段と進み,同時に鉄道,道路の交通の便が開けるようになり,産地の小市場は鉄道沿線へ移動して,交通不便な鉄道後背地の産地市場は著しく衰退した。千屋牛馬市もその例にもれず,昭和30年代後半をもって大市は廃止された。千屋では,伯備線の新設に当たり,鉄道ができれば,放飼など牛飼いの環境条件が悪くなるということで,鉄道を敬遠したということであるが,皮肉にもこれがのちになって千屋牛馬市の衰退を招き,ひいては千屋そのものが避地として時代から置きざりにされる形になったのである。
新見牛馬市場
元禄10年(1697),新見藩が新設され,津山から関長治が入国した。松山藩の水谷氏の統治のときは城下町ではなかったので,関氏は,侍屋敷町や商業地区を設けて城下町として整備した。新町に牛馬市場を設け,問屋規定を定めて問屋株売買手続などを整備した。
問屋手数料は,問屋の口銭で,1頭の売買に対し銀3匁の定法で,税金は1頭につき1分定であったようである。
開市日は6月15日から30日までと,駄市は10月15日から30日までとし,その前後60日間は,付近での牛馬の売買を厳禁した。市場の繁栄雑踏は千屋市をしのぐものがあり,領主は開市中警備と保護に努めたという。
新見市場は,阿賀,哲多2郡の産牛の集散地市場で,天保5年(1834)千屋市場が開設されるまでは,この地方最大の市場であった。ただし,郡内でも南部の産牛は松山市場へ追い出すほうが便利なので,松山市場で取引きが行なわれた。千屋市場が開設されてからは,その前市となった。
久世牛馬市
中世後期から農民によって開設された。慶長9年(1604),美作一円を区域とし,毎年運上銀1枚を納めて,津山藩から公認市場となり,その後寛政6年(1794)には牛冥加銀として銀33枚を上納している。
寛政年中(1789-1800)後半に最盛をきわめ,3万頭の売買があった。この市場は松山市場のような藩営のものではなく,民間の半農半商的なものであった。
問屋は8軒で,そのうち最も古いのが後安家(南中屋)である。この屋敷に近く荒神様(商売および牛の神様)があって,ここへ農夫が厄よけに牛を連れて来るので,ここで牛の売買交換をするようになり,後安家が荒神様の近くで牛市をはじめたのが久世市の起源といわれている。久世の宿場町の発展は,牛市によってもたらされたものである。
久世市場は開市が古く,しかも,関西6大牛市として栄えた。のち寛永年間(1624-43)備中松山市場,元禄10年(1697)新見市場が開設されたが,久世市はますます繁昌し,最も隆盛をきわめたのは,寛政年間(1789-1800)であって,大山市の後市として東牛を中継する拠点市場であった。石田寛ら(1958)の『中国地方山間盆地牛市場の研究-岡山県久世牛市の場合-』によれば,久世市は11月20日から12月15日までの26日間にわたって開かれる秋市によって代表されるが,この秋市は,はじめの4日間が子牛,次の2日間が西牛を売買し,あと20日間は東牛の取引きが行なわれ,たくましい牡牛が近畿地方へ送り出される一大拠点であった。この市場と中国山地の他の大市場との関連をみると,①大山市場の秋市は10月23日からはじまり,大山秋市の残り牛は11月17日からはじまる千屋市場(西牛市場)で取引きされ,東牛向きの残り牛は11月20日からはじまる久世秋市へ集められた。②出雲横田秋市は主として西牛市場であって,この地方の東牛向きの残り牛は久世秋市へ集められた。こうして,東牛は久世秋市を拠点として「大上り」した。この時期以外の登り牛は「相上り(または合い上り)」といわれた。
河内の国の牛馬市場は,中国山地から送られた牛の中継市場であって,駒ヶ谷牛市(昭和16年,牛の最高販売価格が設けられて,中国産地から牛を集めて商売することができなくなって自然消滅した)には美作,備中,備前,伯耆,伹馬,丹波,因幡などから東牛が集められ,ここを中継として,河内,大和,紀伊,伊賀,伊勢方面へ転売されたが,ここには久世東牛を専門に扱う南中屋の設備があった。
一宮牛市(作州)
久世市場と並んで登り牛を送り出す中心市場であった一宮牛は,慶雲2年(705)に開設された最古の市場であって,牛馬の守護神である中山神社鎮座のとき,四方から引いて集った牛馬を売買したのにはじまった。この市場については,石田寛(昭和36年)の「明治以後「登り牛」の流通構造-大登り,相登りを中心にして-」に詳述されている。明治15年(1882),全国市場調査表『農務顛末,第4巻』によれば,この市場は牛およそ1,300頭,馬200頭の取引きで,久世市をしのぎ,作州第一の市場で,出雲,隠岐,伯耆,因幡,備中の牛が入場していた。
享保11年(1726)の『作州記』によれば,牛馬市立の村は,倉敷村(現美作町),釘貫小川村(現湯原町),上徳山,中福田村,(以上現八束村),北野村,梶並中谷村(現勝田町),西一の宮村(現津山市),藤森村,土居村(以上現湯原町),下岩村(現勝山町),久世村,三坂村,以上(現久世町),福渡村(現建部町),下町村,鹿田村(現落合村)の15ヵ所となっているが,明治15年(1882)には全国的にも有名な久世,(現久世町),一宮両市場のほか釘貫小川,(現湯原町)鹿田(現落合町)の4市場だけが記録に残っていた。
この市場は,久世市場と同じく「登り牛」の送り出しの中心市場として繁栄したもので,大正4年(1915)岡山県内務所の『岡山県畜産要覧』によれば,「現在もなお継続し,松山市場と相対して降盛なり」ということであった。明治43年(1910)家畜市場法(法律第1号)の発布により常設宮の市家畜市場となった。
伯耆大山牛馬市
大山博労座は,享保9年(1724),伯耆日野郡大河原(現江府町)の寺侍吉川右平太によって組織的に改革され発展したという。この市場は,中国地方に広がった大山講の講中の参拝する農業守護神であって,祭礼には備前,備中,備後,伯耆,出雲,石見,美作,伹馬,播磨,隠岐,因幡,安芸,讃岐の13ヵ国の商人と牛馬が集まり,江戸末期にはその商圏は東は大阪,南は四国,西は九州に及び,主として卸売人と小売人との接触する大市場であった。
大山博労座に集まる商人には購入側と売却側とがあった。購入側博労には,上方博労と備前博労とがあった。上方博労とは,中国山地から上方牛(東牛)を上方市場へ送る商人のことで,地元商人の上方市場へ売りこむ者と,上方商人の買いこみに来る者とがあった。上方博労の取引頭数は多く,1人で数10頭から100頭近くに及んだ。備前博労は,上方博労の規模を小さくしたようなもので,はじめ備前から牛馬の購入に多数来山したのでこの名称がつけられたが,のちには備前はもちろん備中,備後その他の山陽方面の大博労がこの名で呼ばれるようになった。備前博労は100名をこすほどの人数で,これらの手にかかって山陽方面へ流入する牛馬が,江戸時代には1,000頭以上だったといわれている。
販売側のおもなものは,隠岐牛,伯耆牛,日野牛,備中牛,出雲牛,石見牛,仁多牛などであった。その他にも山陽地方,中国地方,伹馬方面からなど,中国,四国,九州各方面から牛馬が多数集まって,あたかも牛馬の百貨店のような観を呈したという。
開設当初は,博労産へ登って来た者は,随時適当な場所に宿泊していたが,年とともに同国のもの同志がそれぞれ一定の宿泊所に集まるようになり,備前産,備中産,備後産,日野産などと博労宿の固定化による座が成立した。
開市の回数と時期についてみれば,開設当初は春の大山祭だけ年1回(5月23,24日)であった。のちに秋大山に秋市が開かれて年2回となり,ついで江戸末期には7月大山市として7月14-16日開市するようになった。明治9年(1876)10月市を開き,同34年(1901)には4月市を新設し,年5回,開市日数延15日となった。
森本(昭和46年)の『新庄村史(後編)』によれば,同村では昔から子牛の導入は大山市からのものが最も多かった。大山市は日本一で,牛だけで1万頭前後集散されていて,新庄村からは,多くは旧6月,8月,9月二三夜のころ買入れに山へ登った。買入れはおもに子牛で,これを1年間放牧し,翌年旧10月に備中千屋市へ売るものが多かった。明治初年になると大山市は凋落し,各地にせり市場が開かれるようになったので,大正5,6年(1916-17)ごろから伯耆根雨,溝口方面からの導入に変った。大山市は昭和12年(1937)春の大市を最後として,最盛期2万頭の取引きを行なった日本最大の牛馬市も,ついに1,000年以上の歴史の幕を閉じたということである。
久井牛馬市
備後久井(杭)牛馬市は,応和(961-963)のころ(一説には天暦5年(951年)という)備後国御調郡江木村(現久井町)に開設されたもので,安芸,石見,備後,備中から牛馬が集められ,最盛期には牛約5,000頭,馬約1,200頭が取引きされた。販売先は東は畿内一円から西は九州(豊前,豊後)に及び,南は四国への牛の仕向け市場として,備中松山市場とともに拠点市場であった。伯耆大山牛馬市につぐ全国第2の規模をもつ市場で,石見の出羽牛市場とともに中国三大牛市の1つであった。
明治34年(1901)に山陽鉄道が下関まで開通し,市場立地に変革が現われ,尾道市場が全国屈指の大市場に発達して行くのに反して,この市場は漸次衰微し,昭和30年代なかばついに廃止された。
3.牛の流通
近世末期には,中国地方の産牛地では中継地市場が多数成立した。備中,伯耆など先進的な産牛地においては,西牛,東牛のように仕向先による牛そのものの分化さえみられた。中国地方において,近世後期には大家畜商,大牛持ちの市場における実権が強まるにつれて,領主の市場統制は後退せざるを得なくなった。
近世になって,京都への東牛の産地としては,因幡,伯耆,長門,備中などが挙げられていて,中世のころとは著しく異っていた。
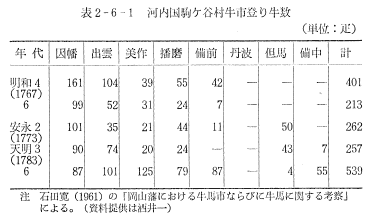
天正年代(1573-91)以前から開かれていた摂津天王寺村の牛市を中心として,中国地方からの「登り牛」の受入れ中心市場は,河内国古市郡駒ヶ谷村および大和国南葛城郡蛇穴の牛市であった。同年代に石橋孫右衛門の『相牛秘伝』にでてくる「登り牛」の産地は,備前,備中,伹馬,丹波,播磨,因幡,紀伊,讃岐,小豆島その他の四国などとなっている。登り牛は天正11年(1583)羽柴秀吉が大阪城の造営に当たって徴発したものが含まれていて,当時の天王寺牛市の発足の基礎は,これに負うところが多かったと考えられている。石田寛(昭和36年)の「明治以後「登り牛」の流通構造-大登り,相登りを中心にして-」によれば,備前国和気郡藤野村(現和気町)の牛市から,河内国駒ヶ谷牛市へ,近世中期には盛んに登り牛を送り出していて,上方博労(東牛または上方牛を専門に取り扱う博労)組合へ加入していた者の名前が列挙されているが,天明のころ(1781-88)から備前の登り牛の比重が低下し,作州の比重が高まったとしている。
登り牛の地域的分布と時代的推移について,明治2-11年(1869-78)までは,美作博労が博労仲間の中心をなしていたが,明治末期から大正にかけて備中博労の比重が高まっていった。
中国の産牛地から畿内向けの牛の移出は,元禄(1688-1703),享保(1716-55)以降盛んになった。作州久世市場からは,車牛が河内国駒ヶ谷市あるいは大和国針ヶ別所市を経由して,これらの地方に送られた。
九州産の牛が,近県末期には車牛として盛んに畿内へ送られたが,備中の家畜商が,豊後牛を和船に積んで兵庫へ運んだ。このようにして,備中は直接近畿への移出地であったとともに,中継地でもあった。豊後では近世後期には,よい子牛を生産すると「備中向け」と称して備中から商人の来るのを待って売った。「備中馬喰善三郎兄弟打連れて豊後に来り,多数購入し,和船に積んで兵庫,東京などへ売った」(『大分県農林誌,畜産業編』(1929))ということで,大分県産牛を本州へ移出するのに備中博労が関与していた。
千屋牛馬市場が開設(天保5年)されてから間もなく,その東からの経路に当たる菅生(現新見市)に,その地の牛を千屋へ行く商人に買い取らせるための菅生市場が開かれた。当時,このような市場が,小坂部大佐(現大佐町)に,北の伯耆との交流地点に当たる高瀬野原や油野(現神郷町)に,また,隣接する作州美甘に,千屋の前市として市場が開設された。
備中,備前産の牛の多くは西牛として,備後,安芸,石見の津和野あたりまで各地に移出され,大百姓に役牛として利用された。この地方は花田植(供養田植)が盛んに行なわれたので,「角の細目な新円形のもので,顔の美しい,顎,肩,前肢まで,前躯のすぐれた」牛が好まれた。これに対して畿内(大和,河内,近江,紀伊北部)向けの後牛は,車牛すなわち上方牛といわれ,性質温順,強健で,粗食に耐え,体格の大きい,力の強いものが好まれ,作州をはじめ備中からもこれに向く牛が仕向けられた。また,近世後期から明治初年にかけて讃岐の砂糖製造場の石臼をひかせる牛も備中,備前から移出されたが,これには讃岐牛といって体が小型で力の強い従順な牛が要求された。
産地市場は,ほぼ1日行程(牛を歩かせて移動するので,例えば久世-坪井間が1日行程,久世-姫路間は3-4日,久世-大阪間は10日の行程であった)の周辺農村から集まる牛を集散するところに開市されるのが普通であったが,近世末期の備中の産牛地では,きわめて接近したところに小市場が濫立したのが特徴的であった。これらは,多くの牛を小作に出している大牛特(牛馬商を兼ねるものもあった)が,持牛を集めて売るために市を開いたためであった。市日には道路に杭を打ったり,野原の立木などに牛をつないで取引きをした。
4.家畜市場の管理と経営
産牛地である近畿,中国の家畜市場は,はじめ自然発生的に開市されたものを領主が育成し,近世になると,これから徴税し,統制するものが多かった。
近世末期になると,備中,伯耆,出雲など製鉄地帯において,商品経済化を推進する上層農民,家畜商,鉄山師など民間勢力の発展により,市場をこれら民間人によって掌握しようという動きがあった。
市場の経営方法をみれば,近世において比較的早く領主によって開設された地方集散地市場は,牛の売買双方から問屋口銭をとり,領主に対して運上金を納める特権商人による独占的な取引きであった。一方,後期になって農民により形成された中国地方の産地市場の多くは,家畜商および農民が自由に取引きできる市場がおもであった。
元禄のころ(1688-1703),摂津天王寺牛市(明治2年廃場)をはじめ駒ヶ谷牛市などでは,売買双方から1頭につき銀2匁ずつの市料を特権商人である石橋孫右衛門らが徴収した。彼は寛保のころ(1741-43)以降冥加銀を上納している。
寛永のころ(1624-43)領主が開設した備中松山市場では,町年寄中曽屋が市場の経営取締りに任ぜられ,牛口銭を徴収したが,市日の売買事務は,その配下の数軒の博労宿の亭主がとった。元文のころ(1736-40)から寛政のころ(1789-1800)の記録によると,牛1頭の売買に対する問屋の口銭は,銀3匁の定法で,運上は1頭につき1分定であった。
元禄のころ(1688-1703)領主によって開設された新見市場においても,領主の定めた問屋株が売買の仲介をして問屋手数料をとった。
近世末期になると,例えば伯耆大山市でも市場手数料(入場牛馬1頭につき銀1分)だけとるということで,事情は著しく変った。中国地方生産地の小市場の多くは,村方の者から市中の問屋が選ばれ,これが市場開設一切を準備し,管理して,売買双方から一定の市場手数料をとるのが一般的となった。
近世末期備中小坂部および坂本の鞍下市場をはじめ,街道筋に牛をつないで取引するような生産地の草牛市は,集った牛がそこで取引きされるだけで,杭銭(市場手数料)を支払うことはなかった。
農民や産地商人が,牛を交換するとき,問屋口銭や市場手数料の徴収のがれに,市場外取引きまたは庭先取引きする場合もかなりあった。
5.牛の価格
古代における牛1頭の値段は,500-700文(天平宝字4年(760ごろ)から13-17石(天喜5,6年(1057-58ごろ)であった。天平宝字4,5年(760-61)のころ,白米1石(現在の40斗)の価格が500-600文であったから,大体白米1石(現在の4石すなわち10俵)であったことがうかがえる。同6年(762)のころ成年男子1人1日の賃金は10文であったことからすれば,当時の牛価はかなり高かった(佐伯有清(昭和42年)『牛と古代人の生活』)。建永のころ(1206)阿波牛1匹が田地1反歩に相当し,嘉永のころ(1225)馬1匹が田地約50歩で売られているのに比較して牛は相当高価であった。
寛政のころ(1460-65)備中新見荘で,領家である東守が百姓の年貢未進のかたに牛を質としてとったが,質流れ牛3頭の売却価格は,それぞれ655文,600文および450文であった。このころから約100年前の元弘のころ(1331),この地方の米1升の価格は銭10文であり,また約150年後の慶長(1596-1614)のころの一般米価は,銭約16文であったから,当時の米価を1升約10文と考えると,牛1頭は米5-7斗ぐらいということになる。
元文(1736-40)から寛政(1789-1800)のころ,備中新見市場における,ある問屋の牛買入れの覚書きから換算した牡牛の価格は,1頭は180匁,他は504匁と520匁であり,ほかに春子1頭228匁,性別不明のもの211匁であった。安政5年(1858)備中釜村(現阿哲郡神郷町)田口源助が貸金のかたにとった子牛は40匁であったので,売渡条件の違いを考えても,前記新見市場の牛価は著しく高かった。繁殖基礎牝牛の価格は,子牛約200匁,成牛約500匁ぐらいと考えられ,一方,京都の平均米価を1石約70匁とすれば,牝牛1頭はほぼ米7石に相当したことになる。
近世末期,出雲の卜蔵家が,備中竹の谷蔓の牝牛を100両で買ったといわれているが,これを銀に換算すれば,約6,500匁となり,普通の役牛価格の数10倍であった。
米価と比較して,牛1頭は中世の6-7斗から,近世末期の1.5-2石ということは,ほぼ水田の反当収量に相当する比価をもって推移したといえる。(斉藤英策(1965)『近世和牛経済史』)
牛価と米価のかなり明らかな資料の得られる1,200-1,300年ごろから,中国地方の牛1頭の対米比価は,1,400-1,500年代以後一貫して牛価が割高であった。このころ牛1頭は米6-7斗に相当した。幕末ごろになると1,5-2石に相当するようになった。このことは,1,800年代後半の安政,文久(1854-64)まで続いた。昔から「牛1頭米10俵,牛10頭家1軒」ということで,牛は農家にとって高価な財産であった。