|
ホーム>岡山畜産便り > 岡山畜産便り1998年9月号 >肉用牛の育種価の利用状況について |
|
ホーム>岡山畜産便り > 岡山畜産便り1998年9月号 >肉用牛の育種価の利用状況について |
平成10年5月までに収集された技肉成績8,672件を基に第9回育種価を評価しましたのでその概要を報告します。
1.育種価の推移について
①育種価判明頭数及び供用中繁殖雌牛に対する判明率とも順調に増加してきており,特に判明率については全国で1,2を争う状況にあります。(表)
このことは,本県が早くから育種価による改良に強力に取り組んできた結果と いえます。
近年の判明率は,やや停滞気味でありますが,繁殖雌牛の更新状況及び若い雌牛の判明状況から考えて問題はないと考えます。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
種雄牛 |
70 |
149 |
153 |
188 |
215 |
283 |
242 |
252 |
285 |
| 雌牛供用中 |
- |
2,315 |
2,322 |
2,488 |
2,986 |
3,047 |
3,075 |
3,124 |
2,911 |
|
| 雌牛評価全体 |
2,544 |
3,993 |
4,395 |
5,462 |
6,387 |
7,333 |
7,517 |
8,078 |
8,679 |
|
|
|
- |
31.6 |
35.6 |
38.1 |
46.9 |
54.1 |
54.6 |
55.5 |
55.8 |
|
|
|
8,110 |
7,320 |
6,530 |
6,530 |
6,360 |
5,630 |
5,630 |
5,630 |
5,220 |
|
|
|
性の効果 |
|
|
|||||||
| 年次効果 |
H元~ 5年 |
|
|
|
9年 |
10年 |
||||
| 肥育地の効果 |
|
←肥育農家の 効果→ |
||||||||
| 遺伝率 | 枝肉重量 |
43.0 |
33.0 |
19.0 |
17.1 |
37.7 |
43.1 |
44.6 |
32.5 |
30.4 |
| ロース芯面積 |
28.0 |
28.0 |
21.0 |
44.0 |
49.8 |
46.8 |
46.4 |
34.7 |
36.2 |
|
| バラ厚 |
19.0 |
28.0 |
34.0 |
27.0 |
34.2 |
41.7 |
40.4 |
36.3 |
34.2 |
|
| 皮下脂肪率 |
29.0 |
35.0 |
46.0 |
40.9 |
41.0 |
44.4 |
45.9 |
42.7 |
40.2 |
|
| 歩留基準値 |
23.0 |
22.0 |
25.0 |
53.3 |
43.5 |
42.6 |
44.2 |
41.0 |
39.7 |
|
| 脂肪交雑 |
25.0 |
29.2 |
31.0 |
48.1 |
48.2 |
53.1 |
52.5 |
47.5 |
44.6 |
|
②枝肉重量育種価について,繁殖雌牛の生まれ年ごとの推移をみますと,平成3年生まれまでは順調に改良が進んでいましたが,近年は下降気味になっています。(図1)
これは改良の重点が,重量型から肉質型に転換された結果であると考えられ,重量タイプとして全国の評価を得ている岡山和牛としては好ましくなく,今後は枝肉重量も改良の重点形質として考慮していく必要があります。
③ロース芯面積育種価は,順調に改良が進んでいます。(図2)
岡山和牛のロース芯面積は全国でもトップレベルであることから,この形質が低下しないよう改良を進めていく必要も指摘されます。
④脂肪交雑育種価についても,順調に改良が進んでおり,特に肉質の改良に重点が置かれた平成3年以降生まれの繁殖雌牛の伸び率は著しいものがあります。(図3)
⑤岡山和牛の近交係数が,近年急上昇しています。将来にわたって改良を進めるためには,遺伝的多様性を確保する必要があり,このための集団の近交係数は,3%以内とすることが望ましいとされていることから,系統が固まり近交係数が高くなったものについては,他係統の血液の導入を適度におこないながら岡山和牛の特徴を損なわない交配が必要です。そのための種雄牛として,安達系の「西勝」清国下前系の「赤木1」,他県の血液の入った「稔糸茂」「利花」「沢幸土井」等が繋養されています。(図4)
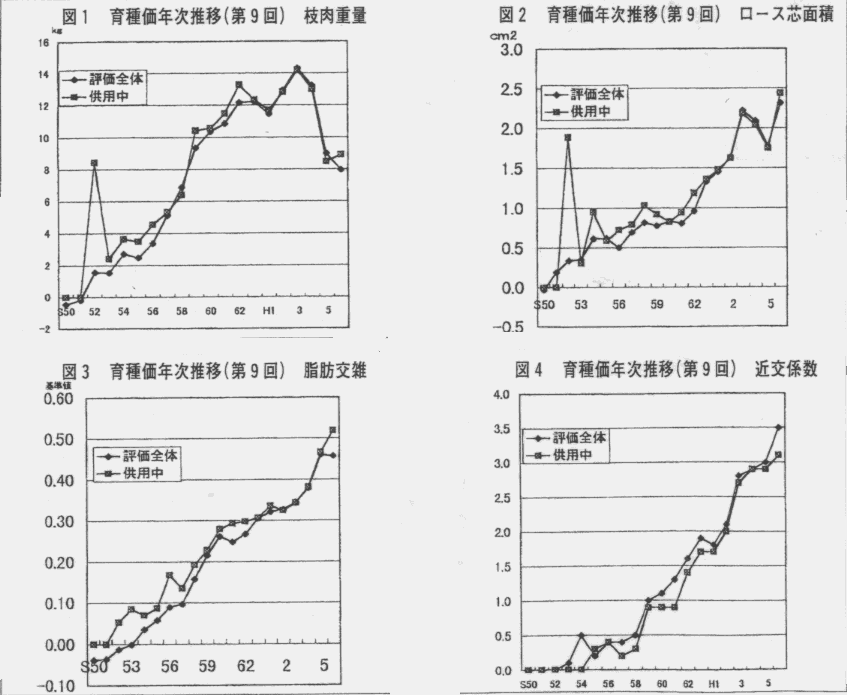
2.枝肉形質の遺伝率と環境の効果の変遷
①遺伝率は,育種価で現わされる遺伝的能力値と実際の枝肉成績との,かい離の度合いを現わしているもので,一般的には30~40%であると考えられていますが,中では脂肪交雑・皮下脂肪厚・ロース芯面積は比較的高めであるとされています。育種価評価ごとに算出された各枝肉形質の遺伝率の推移を示しました。(表)
②本県では,より正確な育種価評価をおこなうために,枝肉成績の収集状況からBLUP法に用いるモデルを検討し,第4回育種価から性の効果を取り入れ,第8回からは肥育地の効果を県レベルから肥育農家レベルに移行し現在に至っています。(表)
③現在収集されている枝肉成績の状況(特に脂肪交雑)を検討すると,枝肉成績を評価する場所(と畜場の効果)によってかなりの差がでてきていることから,この効果も育種価評価モデルに取り上げた方が,より正確に育種価が評価されるものと考えられます。
3.育種価の活用面と留意点
①育種価による岡山和牛の改良の成果をみるものとして,地域別に育種価の推移を枝肉重量・脂肪交雑についてみてみます。(図5)地域による改良方針やET技術の取り組みに状況が顕著に現われています。
育種価による改良をおこなえば,確実にその成果が現れます。しかしこのことは「育種価」の活用の方向を間違えば,岡山和牛そのものが短期間に変わってしまう危険性をもっていることに他なりません。 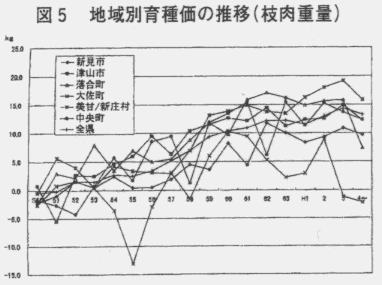
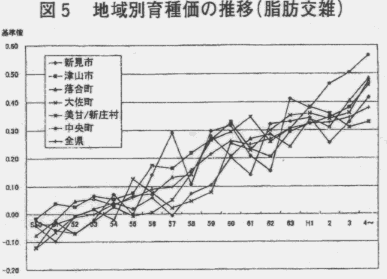
②血統による枝肉成績の状況を枝肉重量・2
②血統による枝肉成績の状況を枝肉重量・脂肪交雑についてみてみます。(図6)
兵庫系種雄牛の交配は,肉質の改良を目的として利用され,確かに肉質の改良は図られますが,2代以上続けて交配を重ねても期待しただけの効果はなく,一方枝肉重量に関しては著しい低下がみられます。
上記の①と併せて,今一度岡山和牛が全国にアピールできるのは枝肉重量であり,ロース芯面積であるということを認識していただき,今後の岡山和牛の改良・交配方法について万全を期していただきたいと思います。
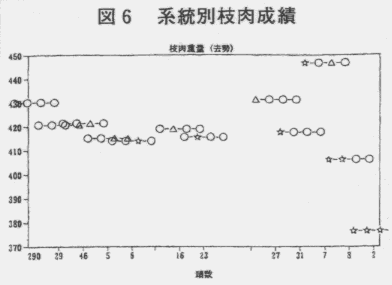
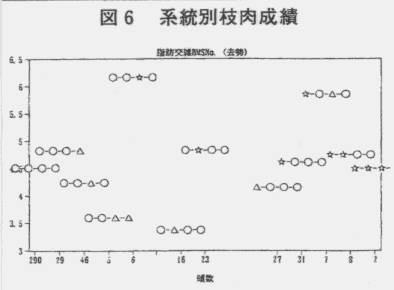
③同じ両親の間に生まれる子牛も「幸運な子牛」と「不幸な子牛」が存在することから(これは遺伝学上さけては通れないもので,このことがあるから両親の遺伝的能力を越える子牛も生まれる。),トップクラスの繁殖雌牛から生まれた雌子牛でも,初産の子牛は雌雄に関係なく肥育農家との連携により肥育し枝肉成績を収集して,早期に産肉能力判定(育種価の判明)をおこなった上で,本格的な基礎雌牛として活用していただきたいと考えます。このことが現在全国トップクラスの本県の育種価判明率を維持し,改良スピードを上げていくことにつながります。