| ホーム>岡山畜産便り > 復刻版 岡山畜産便り昭和26年9月号 > サイロとサイレージ(一) |
| ホーム>岡山畜産便り > 復刻版 岡山畜産便り昭和26年9月号 > サイロとサイレージ(一) |
有畜農業と言う熟語を作ったのは農林省であるか,前愛知県種畜場長の参木晋七郎氏かであるが,この有畜農業と言う言葉と共に急に喧ましくなったのが,自給肥料であり,畜力利用であり,それと関連して又自給飼料が問題となり,遂に小型サイロ(特に小型と称する,大型のものは既に明治20年には日本に入り,北海道の乳牛と共に発達して来たので今更サイロなんて言う必要も無いので大型の物に対しては一時保留するとして)が全国的に取り上げられ,有畜農業係官はサイロの講習に油を搾られたのである。政府が助成し,県が鐘や太鼓で宣伝して廻ったのであるが,喰いついた人間は所詮新物喰いで,造ってはみたもののあの特有な臭いに閉口して出来たサイレージも牛の口に入らないで肥料になってしまったものである。せっかく造ったサイロも蛙のプールとなるか,肥溜となって実際に活用されたサイロは数える程しかなかったのである。然しその後第2次大戦の結果飼料が極度に不足し,農業経営は困難になって来たので再びサイロが検討され活用されだしたのである。
こんなに我が国では問題にされないサイロであるが,サイロの持つ歴史は到って古いのである,サイロの始まりは相当に古い時代からで,エジプトにおいて穀物を貯蔵するために使い出したものが紀元700年頃になってスペイン人がエジプトからローマへこれを伝えたのである,従ってローマの盛んな時代にはサイロを使ってサイレージを作り,これを家畜の冬の飼料に使ったところなかなか成績がよいので,有名なシーザーはヨーロッパを征服する時に,道路の傍にずっと溝を堀ってそこへ飼料を蓄わえて,馬の飼料にしたと言う話がある位である。そうすれば何処へ行っても飼料が用意されているから,そのエンシレージを食って軍馬がどんどん進んで行くことが出来る仕組にしたと言う記事が遺っている位であって相当古くからサイロが用いられたことは事実である。とにかく昔のサイロというのは,要するに穴であったのである。その後になってイギリスや,フランスに於てもサイロの効用を認め,これを実用化するようになって来たのである。殊にイギリスは霧が非常に多い国であって,霧が多い為めに良い乾草が出来ないその為めイギリスではサイロを非常に重要視して相当数建設されたのである。これが西紀1,700年代のころである。この頃ドイツに於てもサイロが研究され又スェーデンのような乾草の出来難い地方に於ても重要視されて相当サイロが建設されサイレージが作られたのである。その後西紀1,700年代の終り頃フランスでサイロに関する著書が現われ,それがアメリカへ輸入された。アメリカではサイロを採り入れるかどうかについて長い間論議されておったが1873年になって,ハッチと言う人が四角なサイロを初めて作った。これによってサイレージと言うものがアメリカに始めて出来たのである。その後非常に研究され,ウイスコンシン大学のキングと言う先生が丸い形のサイロを造ったのが1892年であった。この丸型のサイロが出来てアメリカは世界でも最もサイロが沢山あり,又サイロで成功しておる国となったのである。アメリカではサイロが無ければ経済的に乳牛を飼うことは出来ないと迄言われている。
日本では明治20年に群馬県の神津牧場に入ったのが一番最初で22年には北海道大学に出来ており,その翌年には函館附近の園田牧場が造り,北海道の自然的条件に適した為め全道に拡がり,乳牛と共にその数を増して行ったのである。この様に乳牛と共に発達して行ったサイロも,内地に於てはその経営規模の点より大型のものを造る必要もなく,1ヶ年間の所要量も少く,その上内地農業の特徴である稲藁利用による多年の習慣はサイロの建設を阻む重大原因となったのである。然し戦後の生算費の軽減を考慮した農業経営に於ては飼料の自給は重大なる問題であり,特に草食動物である家畜の飼養の場合は一般に飼料摂取量の3分の2以上が粗飼料であるから,此の粗飼料の質を改善し,貯蔵を完全にすれば,当然濃厚飼料も節約され,従って飼料費も著しく軽減されることになることは明らかであるので,サイロに対する認識も亦改められたのである。最近のサイロ建設に対する一般の要望も大きいものがあるので,新しく建設される方々の為めにその要点を記してみたい。
大きさの決定であるがこれには次の様な事項について研究して自分の家に向く適当な大きさのものを造らなければならない。
所要量の決定には
(イ) 1日の給与量と年間所要量
体重100貫に対して1日3貫位がよいが家畜別に1頭1日当の給与量を示せば次の通りである。
乳牛 5−6貫
役牛 3−4貫
役馬 1.5−2.5貫
緬羊 1−2貫
豚 0.5−1貫
以上の日量に給与日数を掛けると所要量が出る。
(ロ)飼養頭数との関係は(イ)の年間所要量に頭数を掛ければ必要量が出て来る。
詰込材料の豊富な地方ではサイロも出来るだけ大きくし,出来れば年間を通じてサイレージを使用すればよい。
乾草の充分作れる地帯であれば粗飼料は乾草を主体とするか,乾草とサイレージとを半々にすればよいので年間粗飼料給与量とにらみ合せて必要なだけのサイレージを作るサイロがあればよいことになる。
以上の諸点に注意して年間の所要量が決定したらそれに基いてサイロの大きさが決るわけである。サイレージの重さは材料によって異るが大体1立方尺が5貫前後であるから,今サイロの大きさと内容との関係を表で示すと次のようになる
| 深サ | 5尺 | 6尺 | 7尺 | 8尺 | 9尺 | 10尺 |
| 直径 | ||||||
| 4尺 | 310貫 | 380貫 | 440貫 | 500貫 | 570貫 | 630貫 |
| 5尺 | 490 | 590 | 690 | 790 | 880 | 980 |
| 6尺 | 710 | 850 | 990 | 1,130 | 1,270 | 1,410 |
直径5尺のサイロでは深さ1尺に付き約100貫のサイレージが出来ることになる。
上表の容量算出の一例を示すと直径5尺,深さ7尺のサイロに山草を材料としてサイレージを作る場合の生産高は
半径×半径×3.1416(円周率)×深さ×5(山草サイレージの1立方尺の重さ)=生産高であるから
2.5×2.5×3.1416×7×5=690貫となる。
直径は4尺以下になるとホークを使うのに勝手が悪くなるから直径は4尺−5尺位が適当である。直径と深さの関係は1対2位が適当である。直径より深さの方が浅いものは腐敗し易いから少くとも直径よりは深いものを造るようにして頂きたいと思う。
建設の場所の選定については種々な条件があるが使い勝手の良いことを第一条件にしなければならない,然しこれも諸種の事情により支配されるので一概には言えないが大体の条件は次の通りである
毎日の使用であるから出来るだけ畜舎に近い作業に便利な処を選んで設置することが必要である。軒下や納屋を選んでもよいが,日当りの良い所は避けた方がよい。
地下水の低い所を選定しなければならない。地下水の高い所ではサイロの中へ水が滲入し易いので注意を要する。冬期は地下水が低くて水が浸入する心配はないが,夏になって地下水が高くなりサイロの中へ水が溜って利用出来なかったり重石を置いている間は圧力によって水は入らなかったが,重石を除いてサイレージを出し始めたら水が入って腐敗した例はよくあるので,サイロを建設する場合には夏の地下水の高さを,附近の井戸などでよく調査して安全な処へ設置し,地下の深さも決定されたい。地下水の関係によってサイロの型式も決るわけである。
土質はなるべく硬い処がよい。特に構築材料によりセメントを使用する時にあまり吟味しなくてもよいが,セメント代用土(三和土)を使用する場合,或は素掘りでサイロに利用する場合は出来るだけ硬い処を選ぶことが必要である。
サイロの形の方から種類を分けると
(イ)四角形サイロ
(ロ)多角形(八角,六角)サイロ
(ハ)丸形サイロの3種類に区別することが出来る。今日に於ては殆んど丸形になったが,丸形の有利な点は,壁の面積が一番少いから建設材料が経済
に上ることと,角が無い為めに周辺迄一様に圧力が加わるので,サイレージの変質やカビが生えることが無い等の利点がある。
次にサイロの様式により分類すると
(イ)地上式サイロ
(ロ)地下式サイロ
(ハ)半地下式(折衷式)サイロの3種類があるが地上式サイロは建設費用が比較的多額で詰込に手数を要するから家畜頭数の少い農家には適しない(
下水が高い地帯でサイロに水の入る所では地上式でなければならない)地下式サイロは建設費は小額で詰込作業も容易であるが,地下水の高い所では建設作業が困難であるし,地下水の浸透でサイレージが腐敗する虞れがある。半地下式は地下水の高低により,又作業の便,不便によって地上部と地下部との高さを適当に加減出来るから農家にとって最も適した様式である。然し取り出す時の便を考えて地下5,6尺位(人間の身長位)が便利である。或る深さだけ地下に入れることは側圧に対する予防にもなるのである。サイロの中へサイレージを詰めて重石を置くと上から重みが掛って来るから相当の力で側部へ向っても押して来るのである。1立方尺のサイレージは大体11ポンドの力で横へ押すから10尺の深さでは110ポンド,20尺の深さでは220ポンドの圧力がその壁へかかって行くことになるので深いサイロになると相当横へ押す力が強く,従って壁を頑丈に作ることが必要になって来るのである。ところが地下へ入れるとその様な強い力の部分は地下へ入っておるから,横から土が押しておるので簡単な構造であっても充分堪えることが出来るので地下式サイロは非常に安く出来ることになるのである。地上へ1尺乃至2尺位露出させておくと取扱いも容易であるし,雨水が入ることも少く,又人畜が誤って落ち込む様な危険もなく一番よいようである。
次に作る材料によって分けると
(イ)コンクリートサイロ
(ロ)木造サイロ
(ハ)煉瓦サイロ
(二)石造サイロ
(ホ)金属サイロ
(ヘ)三和土サイロ
((ト)素掘サイロ)等に分けることが出来る。各々材料の特徴があり一長一短があるがこの内コンクリートによるものと,三和土のサイロについて造り方の説明をする。
(イ)サイロの型枠
従来サイロを建設をする場合には一基毎に板を以って仮枠を組立てるのが普通であったが,ここの操作は相当の熟練を要するし,経費も相当かかり,素人には取扱いが困難であるので型を統一して団体で同種のものを多数に造る様にして型枠を造っておけで,型枠には相当経費がかかるが,何回も利用出来,サイロの大きさも一定して来るので総ての点で有利であるので型枠を造ることをお奨めする型枠には種々あって単に内枠だけを使用する場合と図に示す様な内枠と外枠とを使用する場合とがある。地盤が硬く形の正しい穴の掘れる場所では内枠だけで差支えないが,地盤が軟かく穴が掘れない場合では外枠が無いと完全なものは出来ない。二重枠を使用する場合には,穴の直径は外枠の外径より約1尺位に大きく掘り,同時に人間の屈み得る程度の掘出しを左右に作って置けば,型枠の組立,除去等に便利である。型枠に用う木材は乾湿何れに対しても耐え得るもので,殊に節孔,割目,腐朽等がなく,圧力により歪撓せず,コンクリートの填充,搗固め等により疵を生しないものを選ばなければならない。乾燥の不充分なもので枠を造ると,之が乾燥した時に板の間は隙間を生じその隙間よりモルタルが漏出してコンクリートの仕上がり面が不体裁になるから注意しなければならない
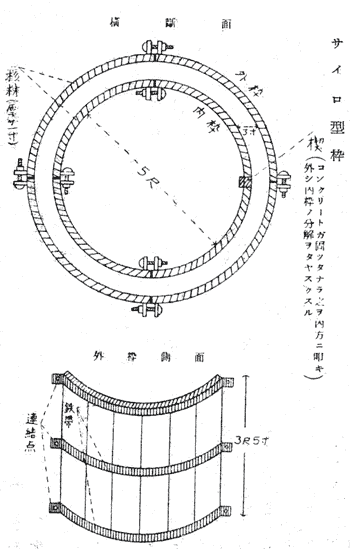
(ロ)コンクリートの材料
(1)セメント。セメントは貯蔵期間により強度に差があり,古くなるに従って強度を減退するものであるから,なるべく新らしいものを使用しなければならない。又貯蔵中に湿気を吸収すると,一部の水和を来たし,甚しく効力が低下するものであるから,此の点も十分注意しなければならない。
(2)砂 砂は清浄で塵芥,土壌,有機物等の有害物を含有しない堅硬,強固,耐久的の石質で,形状は一般に球形がよく,粒の大きさも適当で,更に大小粒の混合程度の適当なものがよい。
(3)砂利 砂の場合と同様清浄で,有機物等の不純物を含有せず,堅硬,耐久的の石質で形状は立方形又は球形がよく軟質,脆弱扁平,細長の石片等を多量に含有しないものを用いねばならない。尚大小混合の程度も適当なものがよい。
(4)鉄筋 地下式,半地下式の場合は殆んど必要はない。土質等の関係で心配であれば稍々壁を厚くするか,丸竹を代用に使用すればよい。地上式の場合は深さ10尺以上になれば鉄筋が必要であるがそれ以下の場合は竹で充分である。壁を厚くすれば竹も使わなくてよい。
(5)水,油,酸,有機物等を含有しないことが必要であるが,普通の水なら大体差支えない。海水でも鉄材を使わぬ場合は著しい支障はないと言われている。
(ハ)コンクリートの混合と構築順序
コンクリートの配合割合は,セメント1,砂2,砂利4,水を適宜(大体使用セメント重量の6割位がよいとされているが,実際には砂,砂利が湿っている場合が多いから,其の使用水量も適宜加減することが必要である)に使用する。先ずサイロの大きさに応じて穴を掘り,底を平にし,栗石等で充分固め,4−5寸位のコンクリート層を造る,この際底面の一部に僅かの凹みをつけて置けば,洗った時等に水を汲み出すのに便利である底が出来たらその上へ型枠を置いてコンクリートを流し込む,周囲の厚さは地磐の硬軟其の他に依り一様ではないが,普通3寸―4寸あればよい。底面と周壁との接着点は特に接着をよくする為めにセメント1,砂1,の稍固練りのモルタルを1寸位入れ,後コンクリートを5寸位流し込み出来るだけ緊密になる様に棒で搗き固める。少し固まったら内枠の楔を外し,取り外し易くしておき,3−4日してから型枠を取り除く。型枠にはコンクリートからよく剥離出来るように使用前にクレオソート,石鹸水等をつけておくとよい。外枠を外したら掘穴に土を入れ,その上に外枠を置き,内枠は下に陥ち込むから3本杭位で支えて継ぎ合せ,継目は水が浸透することのない様に特に入念に行うことが必要で,上縁は清拭して適当に潤した後,上記の様にセメント1砂1のモルタルを2寸程流し込み,後をよく搗き固めながらコンクリートを流し込むとよい,この様に
して順次所定の高さまで継ぎ足してサイロを造るのである。
これは二重枠を用いた場合であるが,内枠だけ使用する場合には,最初周囲を造り,後底面を造るのであるが,周囲に厚薄の出来ない様に,穴掘に特に注意せねばならない。
コンクリートが固ったならば枠を外してセメントモルタル(セメント1,砂2の割合)を塗る,地下水が高く水の滲み込む虜れのある所では,セメントモルタルの中に防水剤を混ぜるとよい。
コンクリートの仕事が終わったならその上に蓆を覆い,日光の直射せぬ様に蔭干しにし,固ったならば水を入れて数日間放置してアク抜きを行う。大体1ヶ月位放置し,使用前には一応水を入れてよく洗った方がよい。又サイロの上縁は地上へ1尺位出して雨水等の流入を防ぎ,その上へ適当な屋根を設け雨露を防ぐのである。
(ニ)コンクリート1立方米を造るに要する各材料概算量(1.2.4配合)
| 材料 | 容量 | 重量 | 備考 | |||
| セメント | 0.45立方米 | 16.17立方尺 | 2.49石 | 3.38瓩 | 90貫 | 6.76袋 |
| 砂 | 0.9 | 32.34 | 4.98 | 6.76 | 18 | |
| 砂利 | 1.8 | 64.86 | 9.96 | 13.52 | 36 | |
| 水 | 0.2 | 7.53 | 1.13 | 2.03 | 54 | |
(この数字は底面厚さ4寸,側壁厚さ3寸,内径4尺5寸,深さ7尺のサイロ構築所要材料と看做して大差ない)
(一)三和土によるサイロ
(1)簡易地上式サイロ
(イ)枠の作成
材料 直径1寸5分位の真竹,これを八つ割りとする,長さ10尺位を適当とする。
直径1寸長さ7−8尺位の丸竹(サイロの深さより2尺位長くする。例えば深さ7尺のサイロを造るとすれば丸竹の長さは9尺とする)但し堀下げをする場合は堀り下げの深さだけ内側に使用する竹の長さを長くする(例えば1尺掘り下げるとすれば内枠に来る竹は1尺長くする必要がある)
(ロ)作り方
サイロの設置場所の中央を起点に必要の大きさの円を画き,更にこの円の外にサイロの壁の厚さを加えた外円を画く,次に内円の中を約5寸−1尺掘り取る(地下水の高い処は5寸位か又はそのままにしておく)この堀り取った土は後から使用するので別な処に保存する。次に掘り取った円の中に栗石を5寸位敷き充分に地固めをする(第1図)次に第二図の如く内円の周囲に1尺位置きに径1尺の丸竹を地下1尺位打ち込む。この場合丸竹の数は必ず奇数にしなければならない。これが終ったらなるべく内円の竹と交互になる様に外円の上に丸竹を打ち込む。次に八つ割りにした竹の表面をサイロの内側に向くようにして内円の丸竹の間を縫うようにして編んで行く(第3図)これが約1尺位の高さになると次は外円の方を編んで行く,この場合は竹の表面を外面に向けておく。この様にして内外とも約2尺位編めた時に次に示す別に用意した叩き土をこの竹籠の内に詰め込み丸棒で充分に突き固めて行くのである。この操作を上部まで繰り返してサイロの壁を作り上げるのである。
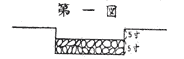 |
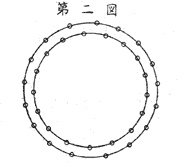 |
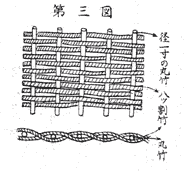 |
(ハ)叩き土の調合割合
調合の良否は直接硬化に及ぼすところが大であるから原土の種類及び品質,砂の大小,石灰の良否等を充分検討の上決定する必要がある。調合割合の標準を示せば次の通りである。
| 材料種別 | 花崗岩質のもの | 玄武岩,安山岩質のもの | 火山灰質のもの |
| 原土 | 70−80% | 50−60% | 60−70% |
| 砂 | 30−20% | 50−40% | 40−30% |
| 消石灰 | 20−25% | 20−30% | 20−25% |
| 食塩又は苦汁 | 1−2升 | 1−2升 | 1−2升 |
(摘要)(1)消石灰量は原土及び砂を加えたもの100に対する割合である
(2)食塩又は苦汁は利用しなくてもよい
花崗岩質原土の風化が充分でないもの又は火山灰質原土で粘質性が充分でないものを使用する時は実際の施工は困難であるから,安山岩質,玄武岩質の原土を併用するとよい。
(ニ)調合方法
原土及び砂は充分乾燥させ,細く砕いて篩に掛けておく。消石灰も同様篩にかける。次に先に示した調合割合によって所要量をコンクリートに使う練板(無ければコンクリートの土間の上)に取る,先ず砂を拡げその上に消石灰を撒布し,充分に空練をし,次いで原土を所要量の半分位入れて空練をし,終ってから残りの半分を入れて同じく空練を充分にする。次に清水(食塩又は苦汁を利用する場合は清水に溶解させる)を除々に加えて更に練合せる。この際水の量は少量で固練り(手に固く握った時塊となり表面に若干水気を感じる程度)にすることが大切である。調合上に特に注意を要する点は調合割合,清水量,空練り及び練合せ等を常に一定にして壁の硬さを均等にすることである。
一基当りの所要量(直径5尺,高さ6尺,側部5寸,底部厚さ2寸5分として)
| 材別 | 花崗岩質のもの | 玄武岩,安山岩質のもの | 火山灰質のもの |
| 原土 | 37−40杯 | 27−30杯 | 32−40杯 |
| 砂 | 17−15杯 | 27−24杯 | 22−18杯 |
| 消石灰 | 50−65貫 | 50−70貫 | 50−65貫 |
| 食塩又は苦汁 | 1−2升 | 1−2升 | 1−2升 |
(摘要)原土及び砂は石油箱1杯量(1,3立方尺)原土及び砂は篩に掛けたものの量であるから原土の種類乾燥程度,細砕の程度等により実際取扱う原土は相当量多くなる。
(ホ)底部作業
側壁の作業中に相当叩き土が底部に落ちるが,底部はよく固める必要があるので更に2寸位の叩き土を入れて充分に叩き固める。特に側壁との接着面は入念に叩く必要がある。
(ヘ)側壁の仕上
表面の凹凸を修正して滑かに形良くすると共に耐久力を増すために粘土モルタル(前記の調合割合に消石灰と清水量を多くして軟かくしたもの)で内側の籠目を塗り込み平滑にする。外側も材料があればこの方法で籠目をつぶすとよいがその必要はない。
(ト)外部の補強
サイレージ詰込により重圧が底部に相当強く掛って来るので底側を補強する意味とサイレージの出し入れに便利な足台とする為めに内円を掘った土を底側に1尺位積み重ね充分固める。この場合中に石を並べておくと更によい。又材料があれば側壁と同様に1尺位竹篭を作り叩き土をもって施工すれば硬化してよい。
(チ)養生
硬化はセメントの硬化理論と同じく水硬性であるから仕上後に水気を切らぬことが必要である。従って濡れ莚等で覆い直射日光を避け充分なる養生を怠ってはならない。
(2)簡易地下式サイロ
これを造る場合最も大切な事は設置場所の地勢,土質等を検討した上,窖の作り方を決定することである。簡易サイロは従来のサイロの建設方法と異り型枠を使用しないため窖の良否は直接サイロの出来上りに影響するからである。設置場所は地下水の低い硬盤質の地帯を最も理想とするが,地下水の高い軟盤質の地帯でも前以ってこれに対する準備をしておけば築造は可能であるが相当技術を要するので前述の地上式にした方がよい。
(イ)窖の側壁勾配
側壁の勾配は設置箇所の土質,原土の種類調合割合及びサイロの壁の厚さ等により決定すべきであるが,概ね硬盤質及び粘土質地帯においては深さ1尺に対し2−3分とし,砂礫質のところでは作業中に側壁が崩れることがあるので3−5分位とする。礫質のところでは側壁に凹凸を生ずる場合が多いので施工上困難であるから施工前に粘土等で側壁面を滑かに修正しておく必要がある。
調合割合,調合方法等は前述の通りである。
(ロ)型枠の作り方
2寸角,長さ4尺のタルキ4本を準備する。これに第4図の如く切り込みを作り更にこれに2本には3寸,2本には5寸の目盛をつける。これを井型に組合て平地に置き使用する。
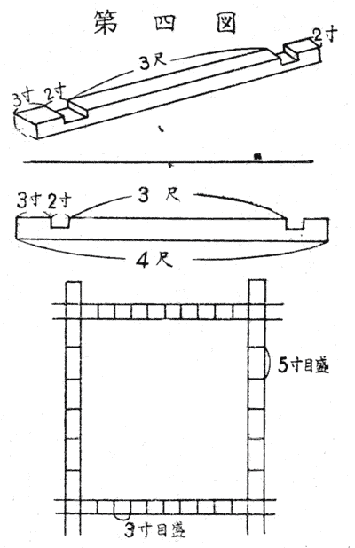
(ハ)型搗き
前述の型枠に前述の原土及び砂,石灰で調合した材料を型枠内に平均に拡げ,先ず軽く踏圧を加え,次に叩き棒で均等に叩き型枠一杯にならして表面を平らにする。
(ニ)切り込み
角型枠に付けた目盛に従って定規を当て寸法を間違えない様に包丁又は鎌で切り込む。縦横に全部切り終ったら角型枠を静かに取除き,一方より鍬をもって順次剥ぎとる。すると3寸×5寸×2寸の大きさの煉瓦様の叩き土が出来る。
(ホ)窖壁作業
(側壁)先の型枠で作った煉瓦を側壁が2寸になる様に横に立てて壁に打ちつけるようにして順序よく一列に並べ側壁に密着させる。側壁との間に空間が出来れば調合した撤土を入れて密着させる。下部第1段が出来たら第2段第3段と同様に置いて行く,この際第1段目と第2段目との継目が同じ所へ来ない様にT字型となるように積み重ねる事が必要である。3−4段位積み重ねた時継目と継目及び窖壁と煉瓦が相に充分密着するように叩き棒で具合よく叩きつける。叩く要領は底部より上方に叩き上げるようにすることが工作上肝要である。側壁の厚さは地下部で1寸5−3寸地上部で2−4寸程度で充分である。
(上部)最上部は2−3寸程度の土石を一列に並べ前記調合によるや,軟い練土で幅6−8寸,厚さ4−6寸程度の蒲鉾型とすればよい。
(底部)地盤の硬軟により土石礫または原土砂,篩粕をもって充分地固め作業をし,前記調合による配合土又は礫を加えた撤土を4−5寸位の厚さに拡げ叩き棒で充分叩くのである。底部の厚さは地磐の状況及び地下水等の関係で加減しなければならないが,概ね2−5寸位でよい。窖を掘って最初に地固めをして,撤土を入れるのは側壁,上部を完成してから入れると側壁との密着がよくいく。
仕上げ,養生等は前述の通りである。
一.築造原理が極めて簡易であるため当業者の理解が容易である。従って普及性が大である。
二.型枠の制約を受けることが少く,一斉的に多数を短期間に建設することが可能である。
三.労力,資材の節約が大である。
四.埋草の必要量によりサイロの大きさを自由にすることが出来る。
五.詰込材料の腐敗率を減少させることが出来る。
この地下式サイロの工築法は直に田畑の肥料溜の構造に応用出来るので便利である。従来の圧厚式築造法に比し遥かに便利で早く出来,壁も一定していて殆んど永年的に使用することが出来るので活用されたい。