| ホーム>岡山畜産便り > 復刻版 岡山畜産便り昭和27年2月号 > 牧野改良と利用 |
| ホーム>岡山畜産便り > 復刻版 岡山畜産便り昭和27年2月号 > 牧野改良と利用 |
中国地方の放牧家畜の大部分を占める和牛の飼料源を見ると第1に野草,第2に稲藁であって,次いで紫雲英が多い。そして濃厚飼料は甚だ少い。このため和牛は一般に蛋白質が不足である。固形物が多く蛋白質,ビタミン類の少い稲藁及び粗剛な野草を良質の草類と置き換えることは今後の重要な問題である。和牛生産地帯に於ては草は主として牧野草であるから,この問題は牧野特に放牧地の改良利用によって解決されねばならぬと思う。
しかしながら牧野は年々荒廃している現状で,この原因の主なるものは過放牧と,牧野の改良に殆んど手が加えられていないことによるものである。
牧野の改良は安易に,早急に,費用がかからなくて行える方法はない。又将来も考えられない。自然に順応して自然の力と協力して改良することが費用もかからず,余り労力も要しない最もよい方法である。
この改良は10年-30年を経て効果を挙げるものであって,エロージョン防止のための草生改良においても5-10年を要するものである。現在中国地方の放野は一面シバが生えているか又は灌木が繁茂している所が多いが,之れは10-20年の結果でなく,30年-50年或はそれ以上の結果であるから早急なる改良は特に困難である。
この困難な仕事は,特に長年月を要するからと言って,そのままで放置してよいものでなくこのまま置けば荒廃の極に達し,放牧不可能になることは明らかである。改良上考えなければならない点について以下述べると次のとおりである。
1.立地条件の同じ様な他の良い放牧場を模範として放牧法,管理法を見做うこと。
2.自分の放野の条件をよく知って改良すること。(特に草種,草量,土壌,降雨量,流水の関係等)
3.荒廃した牧野では現在生えている草を喰いつくされないように放牧,頭数を減らすこと。
4.牧野の年々の変化に注意すること草は毎年同じような草生をしないから年々の状況に応じて放牧方法及び放牧頭数を加減する。特に旱魃の年は草生悪く荒廃するから放牧頭数を減ずる必要がある。
1.過放牧によって荒廃した牧野は直ちによくならない。回復には破壊よりも長期間を要する。
2.放牧頭数をただ1ヶ年の生産量によって,決めてはならない,草生は年々異るからである。
3.放牧は家畜が草を全部喰い尽すまで行ってはならない。
4.放牧頭数を減らすのみでは草生の維持,回復は出来ない。
出入口附近,水飲場附近,通路,其の他放牧畜の集合する所は家畜による喰害,蹄傷はやはり大きい。この防止のためには同一区内に長期放牧をしないこと,休放することがのぞましい。
以下牧野の改良利用上の重な項目について,述べることとする。
1.算出方法 放牧家畜1頭当りの1日の喰草量及び蹄傷量に放牧日数を乗じたものを反当可食部草量(放牧前の可食部草量と放牧中の生長可食部草量の和)で割ったもの。
(イ)喰草量 昼間のみ放牧した時の和牛成雌牛の喰食量は平均36.15㎏である。大迫氏は成馬1日1頭当り喰食量を37㎏と見ている。
(ロ)蹄傷量(蹂躪される量)大体次の様に見てよいと思う。
ササ 喰食量に対する割合 4-5割
ススキ 〃 7-8〃
特に良質なやわらかい草〃 10〃
大迫氏は喰食量と同量の蹄傷があると見ている。
(ハ)可食部草量
和牛では大体次の様に見てよいと思う。
ササ 地際より刈取った場合の約3-4割
ススキ 〃 5-6〃
しかしこれは葉の硬軟,茎の木質化の有無,枯葉の多少等生育の時期によってかなりの差異がある。灌木類では葉及び若芽の部分しか喰しない。従ってその利用率は一般に甚だ低い。
大迫氏は成牛馬1日1頭当りの喰草量及び蹄傷量を各々37㎏合計74㎏として放牧期間中の全所要量を算出し,又他面放牧地の草類最旺盛期に坪刈して,反当総産草量を算出して後者で前者を割ったもので牛馬1頭当り放牧地所要面積を概算している。又林業試験場高萩出張所で12年間実験した結果,年間160日の放牧に於て下の様な結果が出た。但し,長年の使用を見越して40%の面積のゆとりを見た場合で反当生草量370㎏の肥沃度中等の放牧地,牛馬の体重も370㎏位の小格のもの。
幼馬 1町9反0畝
成馬 2,3,7
幼牛 1,6,8
成牛 2,2,6
現在和牛の放牧地は1頭当り面積が1町歩前後或はそれ以下であるにもかかわらず草生の良好でない所がかなりあるが,この点今後大いに考慮すべきである。
即ち牧野に家畜を放牧するには,放牧したい家畜の数によって決定してはならない。放牧地の面積,その年の草生状態によって決定されねばならぬ。
放牧地に放牧家畜頭数を制限したのみでは草生を維持改良することは困難である。即ち全放牧地を1区画として春より秋まで連続して放牧すると草は絶えず喰害され蹂躪されて直接草生が悪化するのみでなく土壌が蹂躪され固化されて悪化しエローションを起す原因ともなり間接的にも草生が悪化する。特に家畜の集合する所の草生は悪化する。このため放牧地は数区以上に区分して荒廃を防ぐために一部を休閑し,又各牧区を順次論換して放牧することが必要である。更に出来得れば草類の再生自然播種を助けるため主要嗜草類の種子結実落下後,或は再生にもっとも影響する時期以外に放牧することが望ましい。
放牧の有無及びその程度が草生にいかに影響するかを次の1例によって見よう。下表の保護区とは禁牧区,中庸放牧区とは1町歩に馬2頭を7月1日より8月31日まで61日間放牧した区,過放牧区とは同様に6月1日より8月31日まで92日間放牧した区であって4ヶ年後の変化である。
主要嗜好植物の草丈平均
| 主要嗜好植物の草丈平均 | 植生密度 4ヶ年後 |
||
| 試験前 | 4ヶ年後 | ||
| 保護区 | 51㎝ | 62㎝ | 100% |
| 中庸放牧区 | 51㎝ | 24㎝ | 62% |
| 過放牧区 | 53㎝ | 15㎝ | 40% |
そして不嗜好性植物のあるもの-アキノキリンソウ,サルトリイバラ,ジャノヒゲ,センプリ等は放牧地に於てかえって増加している。
牧野の草生がよくなりつつあるか,或は悪くなりつつあるかを知るためには草地に於ける草生の連続を知ることが先ず必要となって来る。大迫氏によると我が国に於ける草地の自然的変化は下図の様である。
― →は後退的連続を表す
← …は前進的連続を表す
数字は森林期の肥沃度を100とした場合の比率
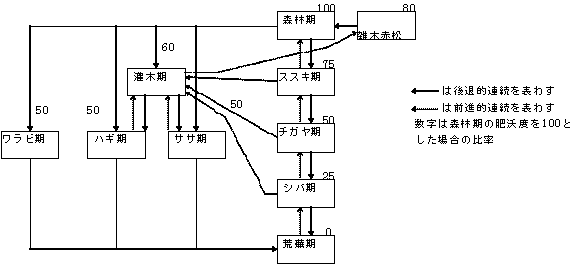
中国地方の放野には純然たるチガヤ期は存在しない様に思われる灌木期,ササ期が多く次いでシバ期,ススキ期が存在する様である。ワラビも相当多く生えている。
上表の草生各期への変化にどの位の年月を要するかと言うと
悪くなる場合
ススキ期よりチガヤ期 5年-15年
チガヤ期よりシバ期 5年-10年
シバ期より荒蕪期 15年-20年
良くなる場合
荒蕪期よりシバ期 5年-10年
シバ期よりチガヤ期 10年-15年
チガヤ期よりススキ期 15年-20年
であって草生の変化は一般に急激に表われず又荒廃よりも改良により永い年月を要するものである。
尚各期に於ける土壌中の有機質をしめすと次の様である。
ススキ期土壌 27.59%
チガヤ期土壌 22.67%
シバ期土壌 19.00%
荒蕪期土壌 11.34%
一般に草地に於て産草量に最も影響する因子は土地の傾斜,表土の深さP.H・置換石灰量等である。
(1)傾斜と草量(坪刈)
傾斜度 平均草量
0-5度 620匁
6-10度 610匁
11-15度 562匁
16-20度 536匁
21-25度 384匁
26-30度 340匁
31-35度 301匁
36-40度 278匁
即ち傾斜角度が大なる程草量が減少している。そして特に傾斜角度20度を界にして草量の著しい増減がある。
(2)表土の厚さと草量(坪刈)
| 表土の厚さ | 草 量 |
| 0-5㎝ | 308匁 |
| 6-10 | 441 |
| 11-15 | 458 |
| 16-20 | 501 |
| 21-25 | 500 |
| 26-30 | 507 |
| 30以上 | 788 |
常識でも明らかな様に表土の厚い程草量が多い。しかし,その厚さが15㎝以上では草量に大差がない様である。
(3)全酸度とネザサ,ススキ,ハギ草量(坪刈)
| 全 酸 度 | ネザサ収量 |
| 0-5 | 350匁 |
| 6-15 | 436 |
| 16-25 | 444 |
| 26-35 | 376 |
| 36-45 | 372 |
| 46-55 | 300 |
| 56-65 | 150 |
| 66以上 | 110 |
ネザサは全酸度0-55の広い範囲によく繁茂するが56以上では草量が著しく減少する。
| 全酸度 | ススキ収量 | ハギ収量 |
| 0-10 | 73匁 | 126匁 |
| 11-20 | 60 | 160 |
| 21-30 | 56 | 166 |
| 31-40 | 53 | 136 |
| 41-50 | 57 | 162 |
| 51-60 | 40 | 130 |
ススキに於ては全酸度0-60まで広く生育するも全酸度の低い程よく繁茂する様である。ハギは全酸度により影響されず高い酸度にもよく生育する野草である。
(4)CaO量とネザサ,ススキ,ハギ草量(坪刈)
| CaO 量 | 0-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
| ネザサ収量 | 265匁 | 293 | 293 | 385 | 450 |
| ススキ収量 | 70 | 82 | 85 | 94 | 80 |
| ハギ収量 | 153 | 143 | 145 | 170 | 160 |
即ちネザサではCaO量の多い程収量多くススキ,ハギでは大差なきも151-200の間に於て収量が最も多い。
(5)土壌の乾湿と草量(坪刈)
| 湿 | 稍湿 | 中庸 | 稍乾 | 乾 | |
| 秋 | 280匁 | 613 | 412 | 395 | 160 |
| 春 | 260 | 502 | 524 | 659 | 125 |
秋草は稍湿った土地に於て収量多く春は逆に稍乾いた土地に於て収量が多い。これを主なる草種別に見ると次の様である。
| 湿 | 稍湿 | 中庸 | 稍乾 | 乾 | ||
| 秋 草 | ネザサ | 100匁 | 370 | 269 | 227 | 5 |
| ススキ | 25 | 36 | 37 | 42 | 120 | |
| チガヤ | 0 | 20 | 40 | 25 | 0 | |
| ハ ギ | 5 | 15 | 37 | 80 | 6 | |
| 春 草 | ネザサ | 140 | 256 | 262 | 392 | 145 |
| ススキ | 15 | 44 | 75 | 102 | 44 | |
| チガヤ | 4 | 2 | 33 | 7 | 15 | |
| ハ ギ | 10 | 30 | 63 | 127 | 40 | |
ネザサ=秋草は稍湿った土地春草は稍乾いた土地に多い。
ススキ=秋は乾いた土地,春は稍乾いた土地に多い。
チガヤ=秋春共に中庸に多い。
ハギ=秋春共に稍乾いた土地に多い。
尚湿地には一般に莎草科,水龍骨科の草種が多く禾本科ではチヂミザサコブナグサ,スズメノテッポウ,クサヨシ,荳科ではクサネム,カワラケツメイ等が存在し,乾地には草種少く,ヨモギ,ススキ,シバ,カルカヤ,トダシバ,アゼクサ,マルバハギ,メドハギ,サルトリイバラ等が存在する。
原野草及び堤塘,畦畔草の種類と乾草成分を見ると次表の様であって原野草の飼料価値が著しく低いことが明らかである。特に蛋白質の不足が甚だしい。
| 植 物 の 種 類 | 固形物 % |
可消化粗 蛋白質% |
澱粉価 % |
|||||||
| 禾本科 | 莎草科 | 荳 科 | 菊 科 | 雑 科 | 隠花類 | 樹木類 | ||||
| 原野乾草 | 77.4 | 2.3 | 3.4 | 3.7 | 6.2 | 3.4 | 3.5 | 86.5 | 1.5 | 18.6 |
| 堤塘乾草 | 79.4 | 2.2 | 1.8 | 3.9 | 11.0 | 1.1 | ― | 86.5 | 3.6 | 25.6 |
| 畦畔乾草 | 60.0 | 19.0 | 0.3 | 3.4 | 14.5 | 0.3 | ― | 86.5 | 4.1 | 26.7 |
原野草の代表的なものをとりその組成と可消化成分を示すと次表の様である。
| 種 類 | 一般成分 | 可消化成分 | |||||||||
| 水 分 | 粗蛋白 | 粗脂肪 | 可溶 無窒物 |
粗繊維 | 灰分 | 粗蛋白 | 粗脂肪 | 可溶 無窒物 |
粗繊維 | 澱粉価 | |
| ススキ | 13.5 | 7.1 | 1.8 | 43.7 | 29.7 | 4.2 | 3.5 | 0.6 | 23.4 | 20.2 | 29.7 |
| チガヤ | 〃 | 7.7 | 2.8 | 41.8 | 26.6 | 7.5 | 4.1 | 1.3 | 24.4 | 17.0 | 31.1 |
| シバ | 〃 | 8.0 | 2.8 | 44.5 | 23.8 | 7.4 | 4.4 | 2.6 | 24.1 | 14.9 | 31.2 |
| カモジグサ | 〃 | 4.8 | 1.8 | 49.2 | 26.5 | 4.3 | 0.2 | 0.7 | 28.4 | 15.8 | 30.4 |
| チカラシバ | 〃 | 5.9 | 1.5 | 43.0 | 27.9 | 8.2 | 0.7 | 0.6 | 22.0 | 18.3 | 25.7 |
| クマザサ | 〃 | 7.0 | 3.0 | 37.0 | 30.7 | 8.9 | 3.6 | 0.7 | 14.4 | 12.2 | 12.4 |
| ハギ | 〃 | 14.3 | 3.5 | 40.7 | 24.1 | 4.0 | 5.8 | 1.1 | 22.9 | 10.5 | 25.8 |
| クズ | 〃 | 14.9 | 2.3 | 28.0 | 35.6 | 5.7 | 9.3 | 0.8 | 23.4 | 10.3 | 27.3 |
しかしながら野草の飼料価値は季節,成育時期により著しく異るものである。一般の野草は春期は蛋白質,脂肪に富み,生育期が進むと共に繊維が増加する。
ススキの組成と季節との関係をしめすと次表の様である。
| 採取時期 | 粗蛋白質 | 粗 脂 肪 | 可溶無窒物 | 粗 繊 維 | 粗 灰 分 |
| 6月 | 11.64 | 4.52 | 48.59 | 27.85 | 7.38 |
| 7月 | 9.93 | 2.56 | 52.43 | 27.49 | 7.55 |
| 8月 | 5.95 | 1.97 | 56.57 | 29.09 | 6.40 |
| 9月 | 5.09 | 2.44 | 56.32 | 28.35 | 8.13 |
| 10月 | 4.23 | 2.71 | 56.85 | 29.18 | 6.86 |
一般野草の飼料価値と季節との関係は次表の様である。
| 刈取月日 | 乾草中の可消化成分(%) | 収量(1a当り) | |||||||
| 粗蛋白 | 粗脂肪 | 可溶 無窒物 |
粗繊維 | 純蛋白 | 澱粉価 | 乾草 (㎏) |
可消化 純蛋白(g) |
澱粉価 (㎏) |
|
| 6 月 20 日 | 2.2 | 1.9 | 26.8 | 14.3 | 1.7 | 30.6 | 8.35 | 137 | 2.56 |
| 7 月 20 日 | 1.0 | 1.5 | 23.7 | 14.2 | 0.5 | 24.7 | 13.41 | 64 | 3.30 |
| 9 月 20 日 | 0.7 | 1.0 | 21.8 | 13.7 | 0.3 | 20.7 | 20.62 | 51 | 4.27 |
上述の様に組成及び可消化成分は季節により著しい変化がある。この為に放牧,採草の適期が或る程度定まって来る。一般に早期放牧,採草は蛋白質に富む,飼料価値の高い草が得られるが単位面積当りの収量が少い。反当澱粉価の収量は後期に於て大であるが蛋白質収量は前期に大である。放牧の一方法であるホーヘンハイム法は草の早期利用及び多量の窒素質肥料,施肥を基として反当蛋白質利用を最大とする方法である。
放牧の有無及びその程度が後年の草生に及ぼす影響については,すでにのべたが更に刈取の及ぼす影響についてのべると1年をきに刈取った場合,毎年1回刈取った場合,年2回刈取った場合につき比較すると,3ヶ年間は収量の差異がないが,その後次第に差が出来5-10年の間で,以上の収量差が表われる。又隔年1回の刈取では草生は減退しないが他のものでは草生が減退する。
この草生の減退は草種の減少,草丈の減少,本数密度の減少となって表われる。即ちススキに於て草丈が年1回刈取区140㎝に対し,年2回刈取区では35㎝にすぎず,コトラード内のススキ本数は前者62本に対し,後者は2本であった。以上の結果から1年休閑するか,或はせいぜい年1回の刈取りに止めるがよい。それ以上の利用には当然施肥その他の草の保護が必要である。放牧に於ても同様で同一牧区に長期の放牧をさけることが必要である特に秋季放牧は少くとも隔年に行うことが望ましい。
又,一般に草類の早期利用は後年の草生を悪化する。しかしササ類では5-6月の利用が後年の草生のためには比較的よい様である。
放牧刈取期は放牧刈取の後年の草生に及ぼす影響,草の反当収量,養分量からして決定されるべきである,がその方面の研究は未だ充分でない。
一般の成長指数を用いて放牧,刈取期が決定されている。
成育過程 成長指数
成長開始(芽の膨張) 5
簇葉の現出 10
葉鞘の膨張 30
花序現出(未開花) 40
満開花 60
種子完熟(一部伝播) 100
この成長指数により30-90の範囲を放牧適期として40-60を採草適期とする。そしてこの指数は放牧草地の主要草にあてはめて見るのである。
家畜の野草に対する嗜好性は,家畜の種類,品種,個体,習性,良草の有無及び程度,季節によって,かなり差があり一概に決定し難いが家畜の品種別では山羊,緬羊,牛,馬の順に次第に食性率が低下している。牛では56-73%の食性率がある。そして一般に禾本科,荳科の草を好み草木の先端部の柔らかい部分をよく食する季節別には春最も嗜好性高く秋が最も低い。今放牧地に於ける和牛の嗜好性を草種別にあげると,次の様である。但し草生状態は中程度で喬木は赤松を主体とし,灌木ではナラ,コックバネ,ヒサカキ等がかなり多く存在し下草はササを主体とし種々の山草が存在するもシバがない放牧地のものである。
嗜好上
(草本)ススキ,ネザサ,クマザサ,チガヤ,ヨシ,クズ,アカクローバー,シロクローバー,スギナ
(木本)無し
嗜好中
(草本)トダシバ,イカリヤス,ハギ,コマツナギ,タデ,ヘクソカズラ
(木草)ムネ,フジ,コナラ,ミズナラ,イボタノキ,ガマヅミ,ウツギ,コックバネ,イヌツゲ,ヒサカキ,フクラハゼ,ヤマナラシ,アキグミ,サルトリイバラ
嗜好下
(草本)メドハギ,ネコハギ,ノアヅキホソイ,アゼガマツリ,サンカクイ,コシンジュガヤ,コウナグサ,アキノタムラソウ,スイカヅラ,アレチノギク,ドクダミ,チゴザサ,エビヅル,ワラビ
(本木)イヌザンセウ,クリ,ヤマザクラ,イノバラ,タラノキ,ヤマツヅジ,ヤブニッケイ,エゴノキ
不食
(草本)クララ,ママコナ,オカトラノオ,アリノトウグサ,キジムシロ,センニンソウ,カナビキソウ,ウラジロツルノシブ,シシガシラ
(本木)ヌルデ,ハゼノキ,ヤマウルシ,ナツハゼ,レンゲツツジ,アセビ,ネジキ,ジヤケツイバラ,アカマツ,カキ,エンジュ,ニハトコ,ヤマモモ,ネヅ
其の他草量少く嗜好性の程度及び食,不食の不明なものが草本で18種木本で2種ある。右に於て特に注意すべき点はメドハギ,ネコハギ,ノアヅキ等の荳科野草で栄養価値のかなり高いものが嗜好性の劣っていることである。
牧野草をより集約的に利用する一方法として施肥が考えられる。3要素肥料の肥効は次の様で窒素の効果最も大で次いで燐酸加里の順である。完全肥料区では無肥料区の3倍以上の収量となっている。
| 生草量(反当) (㎏) |
伸長度 (㎝) |
完全肥料区生産を 100とした比率(%) |
|
| 無肥料区 | 6,188 | 0.48 | 32 |
| 無窒素区 | 8,893 | 0.64 | 47 |
| 無燐酸区 | 11,643 | 0.67 | 61 |
| 無加里区 | 13,243 | 0.73 | 69 |
| 完全肥料区 | 19,076 | 0.88 | 100 |
しかし施肥は肥料の成分により草類の構成に変化を与える点に注意しなければばらない。窒素肥料は禾本科草を増加し荳科草を減少する燐酸及び石灰はこの逆である。野草地に施肥を行うのに1番普及の見込のあるのは石灰,炭カルの施用である。それは草地に於ける産草量を決定する主要な因子として石灰含有量P.Hがあるためであり,又石灰の価格が比較的安価であることによる。
| 乾物1㎏中 | |||||||
| 全灰分 | 石 灰 | 苦 土 | 加 里 | 曹 達 | 燐 | 塩 素 | |
| g | g | g | g | g | g | g | |
| 草の生育のよい土地 | 72.4 | 10.01 | 3.02 | 11.8 | 2.88 | 2.16 | 5.93 |
| 酸性土壌で生育の悪い土地 | 46.8 | 4.95 | 1.86 | 14.6 | 0.61 | 1.66 | 7.22 |
| 酸性土壌で生育の悪い土地 | 51.4 | 6.56 | 2.54 | 7.4 | 1.21 | 2.34 | 3.11 |
石灰施用の効果を無肥料区及び過燐酸石灰区と比較すれば次の様である。(初年度の産草量を100とした場合)
| 第1 年度 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7ヶ年 平均 |
|
| 無肥料区 | 100 | 52 | 52 | 61 | 97 | 100 | 92 | 85 |
| 石灰30貫区 | 100 | 82 | 82 | 132 | 101 | 107 | 146 | 111 |
| 過石5貫区 | 100 | 147 | 147 | 244 | 176 | 208 | 226 | 187 |
一般に我が国の牧野では反当30-40貫の石灰又は炭カルを3-4年に1回位施せばよいと思われる。
尚野草地は夏季土地が乾燥しやすいために土地条件等を考慮,出来得れば灌漑することが望ましい。灌漑の効果は次表の様である。(試験前産草量を100とした場合)
| 試験前 | 初年度 | 2 | 3 | 4 | 5 | 備考 | |
| 標準区 | 100 | 100 | 118 | 127 | 125 | 116 | 灌漑せず |
| 年中灌漑区 | 100 | 142 | 160 | 167 | 167 | 182 | 降雨日をのぞき灌漑 |
| 夏季灌漑区 | 100 | 118 | 120 | 158 | 157 | 186 | 7-9月の間降雨日をのぞき灌漑 |
| 夏季旱魃時灌漑区 | 100 | 106 | 148 | 144 | 148 | 154 | 夏季旱魃のみ灌漑 |
牧野に新しい草を導入する場合,その草の条件として収量多く,柔らかで栄養価値の高いことの他,その土地の自然環境によく適合し,在来の野草との生存競争に勝ちうることが必要であるこの為には次の2要素が特に必要と思われる。(一)肥料少き所にもよく生育すること。(二)夏季の旱魃によくたえること。更に再生力旺盛で放牧畜の蹂躙に強くエローション防止作用をもっていることが必要である。
(以下次号)