| �z�[�������R�{�Y�ւ� > �����Ł@���R�{�Y�ւ菺�a27�N6���� > �S�������{�{������ |
| �z�[�������R�{�Y�ւ� > �����Ł@���R�{�Y�ւ菺�a27�N6���� > �S�������{�{������ |
�@����R��21���C22���̂Q���Ԃɂ킽��C�V�����w���_�Ƌ����g���A�����Âɂ��C�V���s�ɂ����āC�u�S�������{�{������v���J�Â��ꂽ�B�������{�Y�ۂ��珬���C���c���Z�t���o�Ȃ������C���̗v�|�͎��̂Ƃ���ł���B
�@�S�������{�{������i�R��21���j
���z�����
��D�J��̎��@�V�����w���_���A�
��D�_�яȒ{�Y�ǐ��Y�ۋg���Z�����A
�O�D�V�������m�����A
�l�D�����I�C�i���{�{�{����ߓ����Y�F���I�o�j
�܁D��������
�_�яȔ_�ƋZ�p�������@�X�{�Z���u���v�|
�@�Ï��̎������p�ɂ��Ă͖�20�N�O���猤������Ă��邪�C�P���X�N�����̓����P�p�Ȍ�ɂ����ẮC���{�Ŏ������p���ɂ��ċ�̓I�v�悪���Ă�����B���{�ɂ�����Ï����Y�ʂ͔N�Y15�����тŁC���̓��Q�����т͎���������悤�v�悷�ׂ��ł���B�Ï��̎������ɂ͒����Z�p���ł��d�v�ł���B�Ï��͐ێ�12�x�ȉ��ł���ƁC�������s���邩��C�ł������I�ɒ�������K�v������B���H�Ɨp�Ƃ��Ă̒����ł���ƁC�{�����������邩�玔���p�Ƃ��ăT�C���[�W�Ɗ����ɂ��Ē���������@���悢�B
�@���Ï��Œ�������Ɛ��������U���C�{�����Ղƕ��s�̌����ƂȂ邩��C�f�ނ��Q�|�R�������邩�C�m���p�Ƃ��ĉ����ăT�C���ɋl�߂�B�f�������邱�Ƃɂ��`���̕⑫�ɂ��Ȃ�C�m��Y�����邱�Ƃɂ��m�̐������lj����C���̉ƒ{�̚n�D����i�ƌ��シ��悤�ɂȂ�B���Ï������V�ăT�C���[�W�Ƃ��Ē������邱�Ƃ��ł���B
�@���̊O�Ï���ؖ��͐�ɂ��Ċ���������@�����邪�C�J�͂𑊓��v���邩�琠�ׂ��āC�f�������Ċ�������ƁC�`�����W�|10���ƂȂ�唞�ɋ߂������ƂȂ�B�����������f�����́C���k�C�k���̂悤�ȓ��Ǝ��Ԃ̒Z�����ł͍���ȓ_�����邩��C�ނ���T�C���[�W�Ƃ�������悢�B
�@�����p�Ï��̎��n�K���́C�����ŐA�t��T�����C���͐A�t��S���������h�{�I�ɍō��ł���B�i�����Ɩ��Ƃ̂��̍��͑��20������P�����ł���j
�@���Ï��Ɗ��Ï��̎g�p�̏d�ʔ��10�R�ŁC���Ï����Ɗ������̎g�p�d�ʔ�͂W�P�ł���B�ϕ��Ï��Ɛ��Ï��̏������щh�{���l�̑���͂Ȃ��B
�@�Ï��̗{�{�����z�����̍ő�ʂ͎��̊�ɂ��B
�@�T�C���[�W�@�S������70�|75��
�@�������@���@30��
�@�����f�����@���@60��
���{�Ƌ��������@�����A�����u���v�|
�@���a25�N�ɂ����ď���͊Ï�����冋o�̑�p�Ƃ��Ă��̐��ʂ����߂邩�ǂ����ɂ��Ď������Č������C���_�Ƃ��Ă͂��̖ړI�͏[���ʂ���������łȂ��a�{�������Ȃ�C�̗ʂ��傫���Ȃ�C�{���������Ȃ����i�Ï����̋��^�ɂ��j���̊Ï����p�̒����������B�Ȃ�������ɂ�鐬�т͎��̂Ƃ���ł���B
�i�P�j�����z����i��P���P�H�ʁj
| �i�@�@�@�� | ���@���@�� | �@�Ɓ@�� |
| �� | �@30�� | �@�\�� |
| ���� | 30 | �\ |
| ��冋o | 0 | 10 |
| �G�f | 15 | 15 |
| ���� | 5 | 4 |
| �� | �\ | 10 |
�i�Q�j�������ԋy�ы����H��
�@���a25�N�V���P���|12��31�������O�H��50�H����
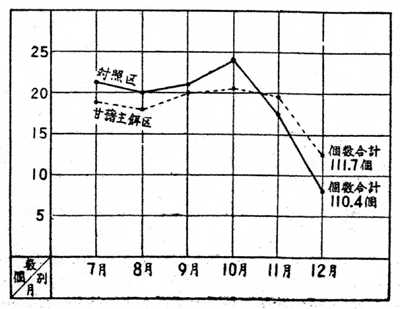
�i�P�j�����z����i�P���P�H�ʁj
| �i�� | ��冋o�� | ���Ï��@������ |
| ���� | �@�\�@�@�� | �@ 33�� |
| ������ | �\ | 100 |
| ��冋o | 35 | �\ |
| ���� | 33 | 33 |
| �n | 17 | 17 |
| ���� | 15 | 17 |
| �ؐ� | 30 | �\ |
| �L�� | 3 | 3 |
| �H�� | 0.5 | 0.5 |
| �e�`�� | 19.11 | 19.01 |
�i�Q�j�������ԋy�ы����{
�@���a26�N�V���P���|12��31���@�����O�C���a25�N11���z���{
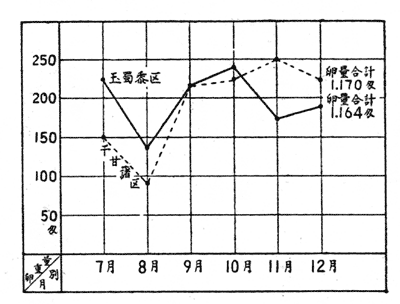
�V����w�@�V�����Y�����u���v�|
�i�P�j�b�����������B
�@��������500�сi�b����20�j��100�т̓b�����l������B����������1,000�сi�b����10�j��100�т̓b�����l������B��冋o�����R�|�T�{�̓b������������B
�i�Q�j���Y�ʂ������B
�i�R�j�ĂƂ̓]���͔|�ɓK���Ă̑��Y�����҂ł���B
�i�S�j���Y������B
�i�T�j���B�^�~���ɕx�ށi���B�^�~���`�������j
�i�U�j�������p�ł���B�i���B�^�~���`�������j
�i�P�j�����������B��������C�A������
�i�Q�j�`�����ܗL�ʂ������B�i�����łT���j���������͍��ށi�`����10���j���悢�B����������ނ����������C���ނ��K�v�Ƃ���B
�i�R�j�@�ۂS�|�S���ȓ��łȂ��Ɨ{�{�����Ƃ��Ė]�����Ȃ��B�Ï�11����冋o�P�������W���C�Ï������R���i����30���j
�i�S�j���B�^�~���a�������B�i���ނ̕��������j
�V�����k�����S���ˑ�
�{�{�g��������
�@�I�퓖����茩��C�{�{�����͌��ݒ������D�]���Ă��邪�C��O�̏�Ԃɖ߂����߂ɂ́C�Ȃ��C�����ʂ̎������K�v�ł��邱�Ƃ͌���ւ��Ȃ��B�������S���A���ɂ܂��Ƃ�����ł͒��X������B����ňꕔ�͍����ɑ��Y�C���C�����e�Ղł���Ï��C�n�鏒�̓b�����𗘗p����Ȃ�C����̎��������������Ɋ��ҏo����킯�ł���B�_�яȂł́C�Ï��������ɑ�p���āC���{�{�{�̕����𑁂߁C�����ė{�{�̐��Y������L���ɂ���ړI�ł�������サ���B�{�{�̉Ȋw���C������������Ă�����������{�{�M���F�X�̕��@�őS���I�ɒ������܂���邪�C������肱��ɒ��Ⴕ�C�ł��O��I�Ɏ��������{�{�̊�Ղ�z���C���s������V������˕����̏��Љ�C�l�@�Ɏ����x���B
�@�ꏊ�͐V�����k�����S���ˑ��厚��˂ł���B���a21�N�������̍����C�ᎁ���Ï�����^����Ǝ��̗{�{������s���C�U�����Y�����т������Ă����̂ŁC����Ƀq���g�������̐l�X�͏����{�{�������������Ĉ��肵����b�̏�ɗ����ė{�{���������C�_�ƌo�c���Ɏ����엿�̓_�ɉ����Ă��L���Ɋ������I�Ɍo�c�o������̂ƐM���āC�c�����C���̖ړI��簐i���C���a23�N��˗{�{�_�Ƌ����g����ݗ����Ă��犈���Ɋ��O�ꂵ�����������{�{���J�n�����B
�@��˕����́C���˂Ɖ���˂ɕ���C�_�ƌː��͏��˂�22�ˁC����˂�13�˂ŁC���v35�˂ł���B���ۗ{�{���s���Ă���̂́C���˂Ŕ_��22�˒��{���{�_�Ƃ�18�˂ƂȂ��ċ���C�S����H���͔����O�̂ݖ�1,800�H�ŁC�ō�300�H�C�Œ�50�H�ŕ���100�H�O������{���Ă��邱�ƂƂȂ�B
�@�k�n�ʐς́C�c��������75�����ŊÏ���t�ʐς͖�W�����C����650�|700�сC700�т͕Ċ��Z�R�Η]�̎��n�������C�i�Ï�������1,000�сj���͐��c����Ŕn�鏒�̓^�}�l�M�C�J���������Ƃ̊ԍ�ł���C��S�����̍�t����������200�т̎��n�������C�Ï����͖ܘ_�C���̑����c�̎��_�p���G���V���[�W�Ƃ��ė��p���Ă���B
�@�I�풼��Ï����Ńq���g�Ĕ��B������˂̂����{�{�́C�O�q�̒ʂ�ł��邪�C�ȉ���������Č������L�ڂ��Č��悤�B
�@��\�{�{�Ɓ@�����C�����̏ꍇ
�P�D���{�@�{270�H�̊O�n�P���C�P���C�R�r�P�������炵�C�Ï��U���C�n�鏒�R���C���씞�T���C���c�Q���V���̍k��ʐς�L���C���݂T�l���_�Ƃɏ]�����Ă���B
�Q�D�����̎����w����
| �敪 | ���@�@�@���@�@�@���@�@�@�� | �w�@�@�@�@���@�@�@�@���@�@�@�@�� | |||||||
| ���� | �P�� | ���z | ���l | ���� | �P�� | ���z | ���@�@�@�l | �P�H�P�� �ێ�� |
|
| �i�� | �� | �~ | �~ | �� | �~ | �~ | �� | ||
| ���� | �\ | �\ | �\ | 493 | 250 | 123,250 | �P���P�H�@5�� | 5 | |
| �n | �\ | �\ | �\ | 690 | 100 | 69,000 | �P���P�H�@7�� | 7 | |
| ���� | 277 | 145 | 40,165 | �P���P�H�@2�� 2�� | 223 | 145 | 32,335 | �P���P�H�@2�� 8�� | 5 |
| ���y | 4,440 | 35 | 155,400 | �P���P�H 45�� | �\ | �\ | �\ | 45 | |
| �n�鏒 | |||||||||
| ���� | 2,955 | 15 | 29,500 | �P���P�H 30�� | 30 | ||||
| �v | 225,069 | 224,585 | 92 | ||||||
�i���j�����̒P���͎s�̉��i�Ɉ˂�C���l���̗ʂ͐��̏ꍇ�Ƃ���B
�@�����w�����@�Ƃ��ẮC�ߋ��T�N�Ԃ̌o���Ɉ˂�N�Ԃ�ʂ��āC�ł������̎��߂�I�ю���v�Z�Ɉ˂鋤���w�����s���Ă���B�����̏ꍇ�͂V�����{���k�C�����w�����C?�̏ꍇ��12���O��{�{�_�����o�R�w�����Ă���B
�@�Ȃ��C�O�\�ł���������悤�Ɏ������͌���50���ł���B
�R�D�����̔z�������y�ы��^���@
| �z������ | �Ï��y�ъÏ����� �G���V���[�W�̏ꍇ |
���^���@ | |
| �n | 7�� | 7�� | |
| �� | ���@45�� | 32�� | |
| �Ï��� | ���@30�� | 21�� | �R���������ϕ����ė^����@ |
| ���� | 5�� | 5�� | |
| ���� | 5�� | 5�� | �[�H���^��X�ɂ���̂��^���� |
| �v | 92�� | 70�� | |
�@���ɓ~�G�͓��v�P���ԑO�ɗ��a��^���C��^�����i�̈Ӗ��ŒZ���a�a�Ƃ��ċ��^����̂ŁC���[�ɂ͋��^���Ȃ��B�A���e�������͎ϕ�����B
�S�D���������쐬��
�@��t�ʐς͑O�q�̒ʂ�ł��邪�C��˂ɉ������t�́C������p���𗘗p���ċ���C50�H����̏ꍇ��W���Ƃ��Ă���̂ŁC��������ɋL���Ēu�����ƂƂ���B
| �����앨 | ��t�ʐ� | ���ʍ�C�� ��ԍ�̕� |
���� | ���� | ���l |
| �� | �T�� | ���� | �@1�� | �@2�� | �����50�H����̏ꍇ�ł��� 100�H�̏ꍇ�͂��ꂪ�Q�{�ƂȂ� 300�H�̏ꍇ�͏�L�̂U�{�ƂȂ� |
| �Ï� | �P�� | ���ʍ� | 650�� | 650�� | |
| ���� | 650�� | 650�� | |||
| �n�鏒 | �T�� | �ԍ� | 175�� | 350�� | |
| �v | �Q�� |
�i50�H����̎����������n�y�ы��^�\�����j
| �T�@���@��@�� | ��t�ʐρ@5�� | 10�l�c�c�c�c�c�c40�ю��n | |
| �@�@�@�@40�с�(�P�H�T��~50�H)��160���� | |||
| �U�@�Á@�@�@�� | ��t�ʐρ@1�� | 650�ю��n | |
| ���@�@��650�� | |||
| �@�@�@�@650�с�(�P�H45��~50�H)��288�����@�G���V���[�W�̏ꍇ�͂P�H32��ƂȂ�B | |||
| �V�@�Á@���@�� | ��t�ʐρ@1�� | 650�ю��n | |
| ���@�@��650�� | |||
| �@�@�@�@650��(�P�H30��~50�H)��433�����@�@�G���V���[�W�̏ꍇ�͂P�H21��ƂȂ�B | |||
| �W�@�n�@��@�� | ��t�ʐρ@5�� | 175�ю��n | |
| ���@�@��350�� | |||
| �@�@�@�@175�с�(�P�H45��~50�H)��78���� | |||
| �X�@�s�����鎔�� | |||
| �@�@�@�@���@���@(365���|160��)�~(50�H�~5��)��51��250�� �@�@�@�@�@�@�̂ɂP�H�P�N�ԕs�����͂P��025��ƂȂ�P�H�P���͂P��025�恀365����2��808�ƂȂ�B �@�@�@�@�@�@��������z�Ɋ��Z�����(�l�i�P��150�~)�~2.8�恁42�K�ƂȂ�B |
|||
�T�D�T�C���̏�
�i�P�j�l�߂鎞��
| ���@�W�����{�@���@10�����{ | 10�����{ | 10�����{ | 11����{ | ���@�@�{ | |
| �Ï� | �T�C����p���� ���̂܂ϕ��g�p |
���� | �T�C���l���n | �� | �@�I�@�@�@ �� |
| ���� | �T�C���l���n | �� | �@�I�@�@�@ �� | ||
| �n�鏒 | �T�C���ɋl���݂������A�̒ʕ��̂悢���ɕۑ�����B | ||||
�i�Q�j�T�C���̑傫���̕W��
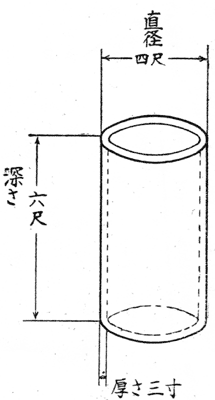
�@��������n������50�H�P�ʂɕt�Q���W���Ƃ��C���̓���͊Ï��P��C���P��̊����ƂȂ��Ă���B
�i�R�j�l�ߕ�
�@���@���̏ꍇ
�@�Ȃ�ׂ����V�̓���I�сC�l�ߍ��ޗʂ��ߑO�����͑O�����Ɋ���ߌ�גf��ɓ���ĂT�����x�ɐ�C���̂܂܃T�C���ɏ[���ɋl���ށB�Ȃ�ׂ��ׂ������ė��a���x�̑傫���Ȃ�ł��悢�B
�@�P�T�Ԍ�ɂȂ�Ɠ��e����R���̂Q�ʂɌ���̂ŁC���̏�ɖ��l���݂S��܂łP�T�Ԗ��ɕ�[���čs���B
�@��������11��10���O��ɋl�ߏI��̂ł��邪���̏d����150�шȏ�Ƃ��d�������т͋X�����B�Ȃ��C���͍גf��P��̔\�͔͂�����P�����̍גf�\�͂�����B
�@���@�Ï��̏ꍇ
�@�Ï��͖������ۑ��������̂�10�����{���l�ߍ���11���̖��܂łɋl�ߏI��B���͂����؊�Ō����P���ʂɔ�����C�����؊�͎�łP����100�ѓ��͂�500�т̔\��������B�����͂P���ʂɍא������̂̂܂܋l�߁C���̋l���̕��@�C�C�̏d���͊Ï����̏ꍇ�Ɠ��l�ł���B
�@�Ȃ��C�Ï��Ɩ���z�����ĂP��ɋl�߂邱�Ƃ͔\����s���Ȃ����łȂ��C�����z���̖������Ȃ��Ȃ�̂ŁC���ꂪ���@�͎��{�����C�S���P��ɂ��ċl�߂�B
�i�S�j�g�p�̎���
�@�Ï����̃G���V���[�W��11�����{���g�p���n�߂āC���N�W�����܂ŗp�����̍�����V���������ɒu��������B
�@���Ï��͎��n����12�����܂Ŏg�p���C���̌�Ï��G���V���[�W�𗂔N�n�鏒�̏o����V����{�܂Ŏg�p�������Ĕn�鏒�ƒu��������B
�i�T�j�g�p���@
�@�G���V���[�W�ނ͏����s�t���g�p�̍ۑS���ςČ�g�p����B���̍ۂ̏��z�������͑O�ɋL�����ʂ�ł���B
�@�Ȃ��C�T�C����肢���y�і������o�����ꍇ���x�̍����S������V�������ɂ́C��w�������s���Ղ��̂œ��ɏォ�珇�X�Ɏ��o���l���ӂ��C���ɑ��̍��ɂȂ�����␅�𒍓����P�T�Ԗ��Ɏ��ւ��ĕ��s��h���ł���B
�@��˗{�{�_�Ƌ����g���́C���̍\�����������C�_�ƌo�c�������I�ɉ��P���邽�ߎ��������y�ю����엿�̍��x���p�ɂ��C���Y�R�X�g���������C�n�ӍH�v�C���͂ȋ����̗͂ł��̖ړI�Ɉ������߂Â����Ɠw�͂��Ă�����̂ł���C�ȏ�̓_���玔���̍w�����Y���̏������ʑ�������������̗͂ŁC���̎�`�ɑ��菈�����Ă���B
�@�{���|��˕����̎Y�����͔N�T���C�P�H�����185�ӂ̎Y���������Ă���B�Ȃ��C��{���ǂ̂��ߓ��u�W��ĂP��������̎����p��{���s�[�^�[�T�C���^�z����P���L���C�헑���͂T�����헑�p�ɂ��C��͋����o�ׂ̌`�Ԃœ����y�ѐX���ʂ֔N�Ԗ�4,000�т̏o�ׂ��s���Ă���B
�@���|�O�q�̒ʂ�z����͔��t���Ă��邪���̎�|�͎�{���Ǘp�ł���D�ǐ���������̂ł��邪�P�����x�͔̔����s���Ă���B
�@�{���|�͔�Ƃ��Ē�����,���c��,���씞�ɍ��x�ɗ��p���Ă���B�{���ɂ��Ă͓��ʂȑ[�u�͌��݂Ƃ��Ă��Ȃ��B
�@�ȏ��G�c�Ȃ����{�{�̌����ɂ��ďq�ׂ����C��˂̂����{�{�͎��g�ŏo������Ǝ��̕��@�ł���ɂ��S�炸�C�Y�����͂T�����ێ����C�����{�{�̂��߂̊Q�͑S������ꂸ�C�p���ĝˎ����͏����C�����̏ꍇ�C40�����G���V���[�W�Ï���^���C71���ɂ��Đ��{�Ɠ����������^������̂ł��邪�C���Y�͑��150�����180���ł���C���Y���̑̏d��400�悩��450��ƂȂ��ċ����Ɍ���̐S�ŖړI�Ɍ����Ă��邱�Ƃ͂܂��ƂɈ̂Ƃ��ׂ��ł��낤���P���i�߂ĉȊw�I���n�ɗ��Ƃ����������̗]�n�͎c����ċ���C�������Čb�܂ꂽ�{�{�̑g�D�I���������p���Ď�{�̉��ǁC���������̑��Y�y�щȊw�I�����C�{�{�Ǘ����������͋ٗv�Ȗ��ł��낤�B
�@�R��22���ߑO�X���V���s���o���C�Q��̃o�X�ŏ�˂Ɍ����B�r���C�V���c�s�O�\��ő�����Y���̎�{������w���C�ړI�n��˕�����12���O�������B�Ă̑�䏊�z�㕽��̍L�傳�͍��X�̔@������ɒl���邪�C�t�������ܕ��̐���̑����Ŗ��ɂ������z��̔��c���L䩊����̏�Ԃɂ��ւ����l�̐S���Â������B���������q�Ƃ͂������ϐኦ��P��n�т̔_�������̔߈����������g�̓��Ɋ����y�n���ǂ����Əd�v�{��Ƃ��Ď�グ���C�k���l���L�̔S�苭���ł��ꂪ���s����^�̗���Ƃ��ė��l�̊�ɉf������̂P����������Ƃ��F�炴��Ȃ������̂ł���B
�@�k�����S���ˑ��͉�X�̊��҂𗠐炸�y�n���ǂ��אڒ������P�����������Đi���P���ł͔��n�]���ɂ����C�����앨��������āC�Ă𒆐S�Ƃ����֍�Ɣ_�Ƌ@�B���ɐ������C�V���n���̐i���I�_���ł������B
�@�������͐V���{�{�n�тŏ��a21�N�������̍����C�ᎁ���Ï�����^����Ǝ��̗{�{������s�������Ƃ��獡���ɔ��W�������Ƃ́C�O�ɂׂ̂��Ƃ���ł���23�N��˗{�{�_�Ƌ����g����ݗ����Ă��犈���ɂ������O�ꂵ�����������{�{���J�n�����R�ł���B
�@���엘�p���w��Ǖs�\�̏�Ԃł������C�������̔_�Ƃ��s���̓w�͂ɂ���Ē����y�n���ǂ��s�����엘�p�������������C���ւ̒n�ړ]���ɂ�莔���앨��D�荞�֍�ő����H���̎����{�{���c�݁C�����̊���P��n�т̔_�ƌo�c�̖ʖڂ���V������̂͑傢�ɒ��ڂɒl����B
�@�ȏア���{�{�̑�̂�\�グ�Ă��̍e���I��B