 >既刊の紹介>岡山県畜産史
>既刊の紹介>岡山県畜産史 >既刊の紹介>岡山県畜産史 >既刊の紹介>岡山県畜産史 |
戦前(昭和10年)のわが国における和牛(役肉用牛)の分布は,西日本78パーセント,中部日本16パーセントおよび,東日本6パーセントであった。馬のそれはそれぞれ30パーセント,12パーセントおよび,58パーセントであった。戦後は,馬に代って和牛の伸びが,とくに東日本で著しく,牛は西日本,馬は東日本という従来からの概念はくずれた。昭和50年(1975)の分布状況を,肉専用種(和牛)だけについてみれば,西日本65パーセント(うち九州47パーセント),中部日本8パーセント,東日本27パーセントとなっている。
岡山県においても,昭和20年代末までは,県の中北部を中心に,ほとんど全県的に繁殖雌牛の飼養がみられ,飼養頭数も年々増加し,昭和30年(1955)2月1日現在には117,000頭と過去における最高を記録したが,その後,農業の機械化により,役利用が後退し,昭和30年代の半ばになると,動力耕耘機の著しい普及により,この傾向はますます顕著となり,役畜から用畜へ乗りかえる傾向が著しく,乳用牛の飼養に転換した農家が多くなって,和牛は減少した。とくに,県南部地帯において,和牛の飼養頭数の減少がいちじるしい。
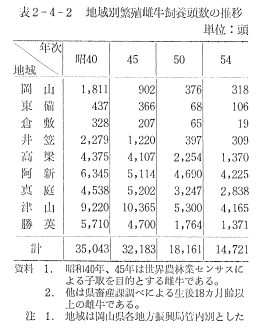
例えば,昭和35年(1960)になると,昭和25年(1950)に比較して,地帯別の和牛飼養頭数の割合は,県南部(岡山,東備,倉敷,井笠の各地方振興局管内)において31.9パーセント減少したのに対し,県北部(高梁,阿新,真庭,津山,勝英の各地方振興局管内)の生産地帯ではわずか8.1パーセントの減少にとどまっている。
昭和40年代の前半になると,山陽線の南側では飼養頭数が激減し,その後半になると,飼養地域はさらに縮少され,姫新線以北の従来から産牛地である阿哲郡,新見市,真庭郡,津山市,勝田郡,久米郡,川上郡の一部が子牛生産地の主体をなすようになった。こうした中にあって,1〜2頭の飼養規模が大半を占めるものの,昭和40年代にはいると,規模拡大がみられ,経営的には副基幹部門として位置づけられ,さらに,一部では専業的な経営も出現してきた。
子牛の育成についてみれば,昭和30年代から40年代前半ごろまでは,総社市,吉備郡,倉敷市,都窪郡などが主要育成地帯であったが,昭和40年代後半になると上房,川上,高梁等の諸郡市がその中心地となった。
