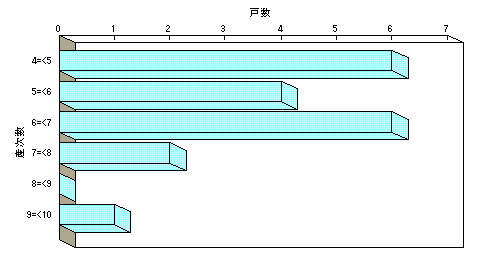>既刊の紹介>肉用牛繁殖経営診断のまとめ>平成13年 >既刊の紹介>肉用牛繁殖経営診断のまとめ>平成13年 |
 >既刊の紹介>肉用牛繁殖経営診断のまとめ>平成13年 >既刊の紹介>肉用牛繁殖経営診断のまとめ>平成13年 |
図20に診断農家の分娩間隔の推移を示した。分娩間隔は平成4年度の13.0ヵ月が最も短く、平成8年度の13.7ヵ月が最も長くなっているが、ここ10年間の平均は13.3ヵ月であり、平成12年度の分娩間隔も13.3ヵ月であった。
ここで、(社)中央畜産会集計の先進的畜産経営技術等実態調査(以下、先進事例とする)の分娩間隔の推移を見ると、平成3年度以降12.6ヵ月で横ばいに推移しており、平成9年度以降わずかながら延長傾向にあるものの、平成12年度は12.9ヵ月で、診断農家の分娩間隔とは0.4ヵ月の開きがあった。ちなみに、先進事例(65事例)には本県の診断農家5事例も含まれており、その分娩間隔は12.4ヵ月であった。
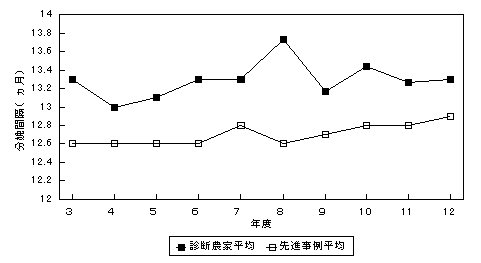
図21に診断農家の分娩間隔の分布を示した。平均は13.3ヵ月となっており、最大は16.8ヵ月、最小は11.5ヵ月で5.3ヵ月もの開きがあった。岡山県の指標である分娩間隔13ヵ月をクリアーしている経営は、前年度と同様12事例(63.2%)であったが、15.0ヵ月以上の経営も前年度と同様2事例(10.5%)あり、改善が望まれる。ちなみに、分娩間隔13ヵ月をクリアーした12事例のうち7事例(58.3%)が前年度と同一事例で、前年度15.0ヵ月以上の2事例はやや改善され、今年度の2事例とは異なっていた。
ここで、分娩間隔が13ヵ月未満の診断農家を見ると、日々の十分な観察や日光浴等によるストレスの軽減はもちろんのこと、早期親子分離を取り入れることで、繁殖成績の向上につながった事例があり、今後の取り組みとして注目される。
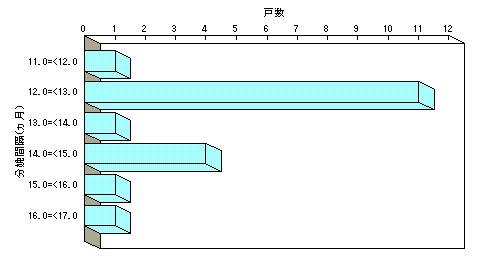
図22に診断農家の産次数の推移を示した。産次数は平成5年度の5.9産が最大で、その後大きく減少し平成8年度では4.8産までなったが、その後は増加傾向を示し、平成12年度は5.8産となっている。平成5年以降の産次数の減少は、育種価を中心とした改良の推進により、高産次で低能力な成雌牛の更新が多かったためと考えられ、逆に平成9年度以降は、優良成雌牛の判明に伴う長期飼養の影響があるのではなかろうか。
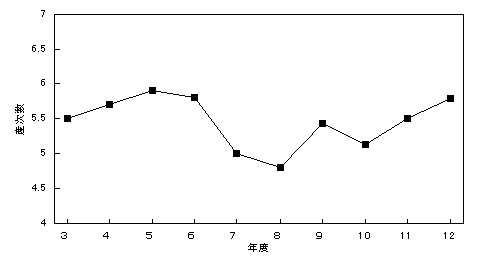
図23に診断農家の産次数の分布を示した。4産以上〜5産未満及び6産以上〜7産未満の階層の事例がそれぞれ6事例(31.6%)で最も多かったが、7産以上も3事例(15.8%)あった。