 >既刊の紹介>酪農経営診断のまとめ>平成11年 >既刊の紹介>酪農経営診断のまとめ>平成11年 |
 >既刊の紹介>酪農経営診断のまとめ>平成11年 >既刊の紹介>酪農経営診断のまとめ>平成11年 |
岡山県には現在,育成牛を含め2,268頭のジャージー種が飼養されているが,図24のとおり,昭和62年から増頭傾向にある。このことは蒜山酪農農業協同組合が,昭和62年からジャージー種の生乳に対して奨励金を出し始めたことによるものである。その結果,ジャージー種飼養農家の増頭のみでなく,ホルスタイン種とジャージー種を飼い,生乳だけは分別出荷している,いわゆる混飼経営で,ジャージーの比率を高めた結果でもある。しかし,ここ3年間ほどは頭打ちの状態であり,平成10年は若干減少している。
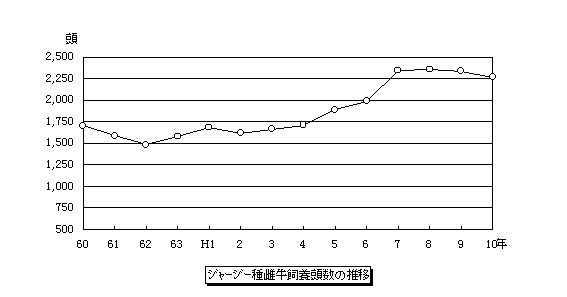
平成10年度に経営診断を行ったジャージー種飼養農家は5事例で,うち2事例がホルスタイン種との混合飼養農家であった。このように対象事例数も少なくジャージー種の飼養割合も異なることから,成績だけを表10〜表13のとおり掲載する。
ジャージー種の経営を概観すると,ホルスタイン種の経営に比べ,飼料自給率が高く,経産牛1頭当たり購入飼料費はすべての経営で300千円を切っている。したがって,ジャージー種の平均乳飼比は40%で,ホルスタイン種の平均53%を大きく下回っている。また,40%を切っている経営が3事例あり,うち1事例は30%を切っている。
また,奨励金は表13ジャージー経営損益計算書の「売上高」のなかの「その他」の項で示しているが,特にジャージー種のみの経営においては生乳売上高の50%近い金額が計上されており,経営に大きく寄与していることが理解できる。
一方,ジャージー種経営の課題として,乳脂率の低さと乳牛更新率の高さを指摘しておきたい。乳脂率は5事例中3事例で5%を切っており,また,乳牛更新率も5事例中3事例でホルスタイン種の平均値である26.1%を超えている。そのうち2事例は30%を超えており,耐用年数が短くなっていることが理解できる。このことは,昨今のジャージー種雌牛頭数の減少に関与しているのではないだろうか。
経営成果では,ここでもフリーストールシステムで他産業従事者以上の労働報酬と農家所得を実現している事例があることに注目したい。